INDUST6月号に「廃棄物処理法改正法案★大分析 ~『意見具申』にみる改正法の基本的視点~」が掲載されました
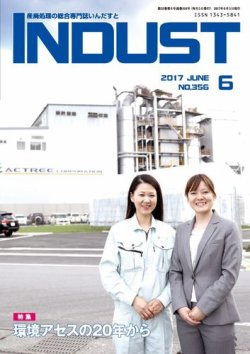
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2017年6月号に「廃棄物処理法改正法案★大分析 ~「意見具申」にみる改正法の基本的視点~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1506597/
廃棄物処理法は5年ごとに見直されており、2010年の改正法施行から5年が経過したことを受け、2016年5月から中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会で8回にわたる議論が行われました。2017年2月14日には「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が環境大臣に提出され、これを基に同年3月10日に改正法案が閣議決定されました。改正法案のみを見るだけでは、廃棄物処理制度についてどのような議論がなされ、どのような方向性が検討されたのかを把握することは難しいため、意見具申に示された視点と法案に実際に取り入れられた内容を分析することが重要です。
意見具申では、廃棄物処理制度の基本的視点として「適正処理の更なる推進」と「健全な資源循環の推進」の二つを掲げています。適正処理の更なる推進には、排出事業者責任の徹底、処理業者による適正処理の確保に向けた仕組みづくり、現場での機動的な対処を重視した仕組みづくりという三つの視点が含まれています。
排出事業者責任の原則は廃棄物処理法の根幹ですが、排出事業者にその認識が十分に浸透していないという問題が指摘されています。処理業者による適正処理の確保については、不適正処理業者の排除とともに、適正処理を行う業者が不適正処理を安価で行う業者より優位に立てる仕組みづくりの必要性が強調されています。また、適正に処理する業者が円滑に事業活動を行えるよう、廃棄物処理制度を合理的なものにする必要性も指摘されています。
現場での機動的な対処を重視した仕組みづくりには、「規制の現場」での行政の迅速かつ適正な対処を可能とする視点と、産業廃棄物処理の広域化に鑑みた法制度の統一的運用という視点があります。特に2016年初めに発覚した食品廃棄物不正転売事件(ダイコー事件)が行政対応の在り方に大きな影響を与えました。
「健全な資源循環の推進」については、排出抑制・適正な循環的利用の推進と、優良な循環産業の更なる育成および各種手続等の合理化という二つの視点が示されています。持続可能な社会の構築に向けては、環境保全を前提としつつ、排出抑制を徹底し、廃棄物については再使用、再生利用、熱回収の順に循環的利用を行うことが重要とされています。
これらの基本的視点に基づき、意見具申では「産業廃棄物の処理状況の透明性の向上」と「マニフェストの活用」を主要な論点として挙げています。
〇産業廃棄物の処理状況の透明性向上
ダイコー事件を踏まえた再発防止策を食品廃棄物だけでなく産業廃棄物全般に広げること、都道府県等による監視体制強化を通じた透明性と信頼性の強化が方向性として示されました。特に、中間処理業者による再生利用の状況を排出事業者が確認できるよう促進することが重要視されています。しかし、これらの方向性は2017年の改正法案には盛り込まれず、今後の検討課題となりました。
〇マニフェストの活用
虚偽記載等の防止と電子マニフェストの普及拡大が課題とされました。改正法では、マニフェスト虚偽記載等に対する罰則が強化され、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げられました。また、一定規模以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者に対して電子マニフェストの使用が義務付けられました。
廃棄物処理法の改正は、単なる規制強化にとどまらず、適正処理と資源循環の両立、事業者の円滑な活動の確保という多面的な視点から検討されています。今後も引き続き、これらの基本的視点に基づいた制度改革が進められていくことでしょう。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
