INDUST9月号に「建設汚泥処理物の有価物該当性に関する取扱いについて(通知)令和2年7月20 日(環循規発第2007202 号)」が掲載されました
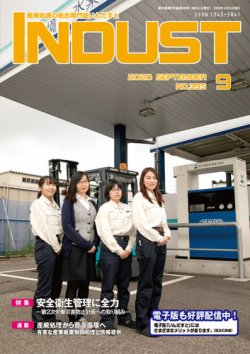
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2020年9月号に「建設汚泥処理物の有価物該当性に関する取扱いについて(通知)令和2年7月20 日(環循規発第2007202 号)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2021021/
本通知は、「建設汚泥処理物」の「有価物該当性」について通知するものです。問題となっている物が廃棄物に該当するか否かについてはおから事件および「行政処分の指針」などから「総合判断説」によって判断することとされています。また、とくに「建設汚泥処理物」の廃棄物該当性については、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」によって総合判断説の考え方から建設汚泥処理物について具体化した指針が示されています。 本通知によって建設汚泥処理物の有価物該当性が示されたことの意義はどこにあるのでしょうか。
「総合判断説」とは、廃棄物に該当するか否かを、「(ア)その物の性状、(イ)排出の状況、(ウ)通常の取扱形態、(エ)取引価値の有無及び(オ)占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべき」とする考え方です。
「建設汚泥処理物」とは、「『建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のもの』に中間処理を加えた後の物」をいいます。建設汚泥処理物は、用途ごとに当該用途に適した性状は異なること、競合する材料である土砂に対して現状では市場における競争力がないこと等から、あらかじめその具体的な用途が定まっており再生利用先が確保されていなければ、結局は不要物として処分される可能性が極めて高く、現状においては建設汚泥処理物の市場が非常に狭い、という特性があります。 そこで建設汚泥処理物については、総合判断説に基づいて廃棄物該当性を判断するべきであるとされています。
本通知が「有価物該当性」について示す趣旨は2つあります。
(1)流入規制の実質的無効化
本通知は、「各種判断要素の基準を満たし、かつ、社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確認できる場合にあっては、建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点において、有価物として取り扱うことが適当である。」とするものです。
建設汚泥処理物が、再生利用される用途に照らして適切であるにもかかわらず、「有価物」とされず、解釈により、再生利用先へ搬入されるまでは廃棄物として扱われる場合があります。その場合、一部の地方公共団体においては、域外からの産業廃棄物の流入について事前協議制等によって流入規制が行われている結果、適正な再生利用が妨げられる懸念があります。本通知はこのような自治体独自の規制である流入規制により再生利用が妨げられるのを防止します。
(2)再生後物の利用方法の拡大
また、「本通知は、建設汚泥処理物等の有価物該当性を判断する一般的な方法を示したものであり、建設汚泥処理物等ではないものについて判断する場合」にも参照が可能とされます。 従来、再生利用が予定された再生後物については、譲受人との間に有償譲渡契約が成立し、かつ、譲受人に占有移転することが必要とされるのが一般的な通知の理解でした。しかし、この通知の考え方が建設汚泥処理物以外についても参照しうるとなれば、総合判断説の各種判断要素の基準を満たし、かつ、社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確認できる場合にあっては、有償譲渡契約等の成立はなく、廃棄物性を卒業することになります。 このことは、処理後物についての自己利用をも容易とするものであり、再生利用に途を開く画期的なものであるといえます。
本稿ではより詳しく解説していきます。
ぜひご覧ください。
