INDUST1月号に「住民同意の問題点と「見直しの方向性」が掲載されました。
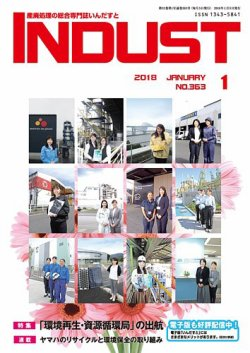
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年1月号に「住民同意の問題点と「見直しの方向性」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1613348/
平成29年改正法制定に先立ち,環境中央審議会より「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が行われましたが,同意見具申における廃棄物処理制度の見直しの必要があるものとして地方自治体の運用について下記のような指摘が行われました。
「実質的な住民同意についても、その実態を把握した上で、廃棄物の円滑で適正な処理を阻害するおそれがあることを通知等により周知するなど、必要な措置を講じる必要がある。」
今回は,この「住民同意」について検討してみたいと思います。
住民同意とは、廃棄物処理施設の設置許可申請に先立ち、施設設置について住民の同意を得ることを指します。しかし、これは廃掃法上の要件ではありません。廃棄物処理施設は国のインフラとして必要不可欠ですが、多くの住民にとって「近所にはほしくない」施設です。そのため、住民同意を法的要件とすると施設設置が事実上不可能になるおそれがあります。代わりに法律では、監督行政庁が施設の安全性や適切性を判断するための詳細な規定を設けています。
それでも多くの自治体は将来の紛争防止や環境保全協定締結のため、事実上の住民同意を求めています。環境保全協定は法令の基準を超えた内容を含むこともあり、一度締結すると民法上の契約として事業者を拘束するため、慎重な検討が必要です。
住民同意の問題点として、平成22年の意見具申では、住民の反対が地域コミュニティを破壊するおそれや処理施設設置手続きの長期化などが指摘されています。地方では地域のつながりが密接なため、賛成意見を表明すると孤立する可能性を住民が懸念し、「賛成」と言えない状況が生じます。これは事業者側では解決できない問題です。
住民同意を要請する法的根拠は「行政指導」に過ぎず、行政手続法によれば行政指導は強制力を持ちません。そのため、住民同意が不可能と判断した事業者は、行政指導に従えないことを表明して設置許可申請を行うことも検討できます。
今後の方向性として、住民同意の即時撤廃は難しいものの、行政が住民説明会に同席して施設の重要性や安全性を説明するなど、より積極的な関与が求められます。平成22年と29年の意見具申では、施設の維持管理情報の透明化によるリスクコミュニケーションの推進や、住民同意が適正処理を阻害するおそれがあることの周知が必要とされています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
