INDUST2025年7月号に「東京高裁2024年(令和6年)10月17日 水質汚濁防止法、下水道法と廃棄物処理法との関係」が掲載されました
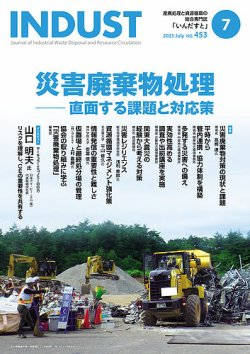
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2025年7月号に「東京高裁2024年(令和6年)10月17日 水質汚濁防止法、下水道法と廃棄物処理法との関係」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/new/
2019年(平成31年)1月24日、排水基準を超える汚水を海に流したとして、食品廃棄物リサイクル工場バイオプラザ名古屋の運営会社である「熊本清掃社」の代表者と工場責任者の2名が水質汚濁防止法違反の疑いで逮捕された事件がありました。
本件は、「工場排水」という廃棄物を不法投棄しているようにも思われます。本件は、なぜ廃棄物処理法違反ではなく、水質汚濁防止法違反に問われたのでしょうか。 2024年(令和6年)10月17日、中間処理施設から排出される汚泥を下水道内に放流させた行為について、下水道法が適用されるのか廃棄物処理法が適用されるのか争われた事案に対する判決が東京高裁でありました。
今回は、廃棄物処理法と隣接法である水質汚濁防止法、下水道法との「関係」(後述)について、判例を参考にしつつ解説していきたいと思います。
「一般法と特別法」
一般法とは、適用対象がより広い法のことを、特別法は、適用対象がより特定されている法のことをいい、一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用されることになります。このような事象を「特別法は一般法を破る」(特別法は一般法に優先する)といわれています。
廃棄物処理法と水質汚濁防止法
廃棄物処理法が不法投棄を一般に禁じた法律であり、これに対して、水質汚濁防止法は、「工場及び事業場」という特定の場所から、「公共用水域」に排出される水の排出を規制した法律であると考えると、廃棄物処理法という一般法に対して水質汚濁防止法はこれに対する特別法であるということになります。
廃棄物処理法と水質汚濁防止法は一般法と特別法の関係にあるのか?
一般法よりも特別法の方が重い刑罰が定められているのが一般です。ところが、廃棄物処理法と水質汚濁防止法は、一般法である廃棄物処理法の方が重い刑罰が定められているという矛盾が生じています。
その理由としては、水質汚濁防止法と廃棄物処理法が制定された当時は、水質汚濁防止法の方が刑罰が重かったにもかかわらず、廃棄物処理法に幾多の改正が行われた結果、廃棄物処理法の方が刑罰が重くなってしまったということがあげられます。
近時、廃棄物処理法と水質汚濁防止法の関係を「観念的競合」の関係にあるとする考え方があります(「特別刑事法犯の理論と捜査⑵」城祐一郎P.218)。二つの法律が「観念的競合」の関係にある場合、ある事象に対して両法が適用され、両法のうち重い刑罰で処罰されることになります(刑法第54条第1項)。
廃棄物処理法と下水道法
⑴事案の概要と問題の所在
汚泥の中間処理を営む会社(A社)が、公共下水道内に産業廃棄物である汚泥及び一般廃棄物である汚水を放流させたという事案においては、下水道法が適用されるのでしょうか、廃棄物処理法が適用されるのでしょうか。
汚泥と汚水は両者とも「廃棄物」に該当することから考えると、本件に対しては廃棄物処理法と下水道法が両法とも適用され、刑罰が重いほうで処罰される「観念的競合」の関係にあるとも解されますし、下水道法が、「公共下水道」内に廃棄物を放流する行為について規制した特別法であると解すると、下水道法は廃棄物処理法の特別法で違反して汚水を放流させる行為については下水道法のみが適用され、廃棄物処理法は適用されないことになります。
本件においてA社の弁護人は、実際、下水道法は廃棄物処理法の特別法であり、本件に対しては下水道法のみが適用されると主張しました。
⑵判例(東京高裁2024年(令和6年)10月17日判決)
ア 実行行為
不法投棄罪では、廃棄物を「みだりに捨てる」の「みだりに」に該当するかどうかは、社会的に許容されるかという観点から実質的に判断されます。
一方、下水道法の排水基準違反罪では、排水基準に違反して汚水を排除することが実行行為であり、その判断は排除した汚水の水質が基準に違反したか否かを形式的に判断されます。
また、不法投棄罪の構成要件が排水基準違反罪の構成要件を包み込む関係にはないとしています。
イ 法の目的
両法律とも「公衆衛生の向上」を目的として掲げていますが、廃棄物処理法は直接的な目的として規定しているのに対し、下水道法は「公共下水道の管理等の基準を定めて下水道の整備を図ること」を直接の目的とし、「公衆衛生の向上」はより高次の目的として規定されています。
また、下水道法は、公共下水道管理者の行政目的を達成するための行政処分の実効性を担保するための刑罰という性質があります。
ウ 下水道法と廃棄物処理法の相違
排水基準違反罪は、基準違反の有無という形式的な基準で犯罪の成否を判断するものです。
不法投棄罪は、主体を限定せず、社会的に許容されるかどうかという観点からの実質的な判断を経て犯罪の成否が決せられます。
両罪は、犯罪構成要件の仕組み、処罰の実質的な理由・目的などの点で犯罪としての性格が根本的に異なるものです。
エ 結論
不法投棄罪と排水基準違反罪は、一般法と特別法という関係にはありません。したがって、公共下水道への汚水の排除行為について、裁判所は不法投棄罪に関する罰則規定を適用することができるということになります。
⑶ 解説
下水道、水質汚濁防止法、廃棄物処理法は同様の事案に対して適用が重複的に問題となるものの著しく法定刑が異なってしまっている現在、一般法か特別法かと一律に分けるのではなく、法の自由保障機能を害しない限り、どの法律を適用することが最も法の目的を達成することができるかという視点で適用を考えてもよいのではないでしょうか。東京高裁2024年(令和6年)10月17日判決の立場に立った場合、バイオプラザ事件についても異なった判決が出たかもしれません。
本稿ではより詳しく解説していきます。
ぜひご覧下さい。
