INDUST2025年8月号に「令和7年6月24日『今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間とりまとめ』その前に!平成29年『廃棄物処理制度の見直しの方向』の検証」が掲載されました
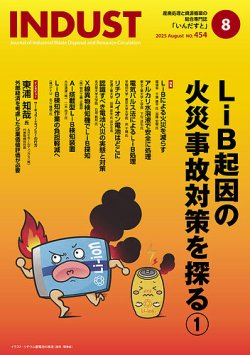
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2025年8月号に「令和7年6月24日『今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間とりまとめ』その前に!平成29年『廃棄物処理制度の見直しの方向』の検証」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/new/
平成29年廃棄物処理法改正附則第5条において、改正法施行後5年を経過した後に廃棄物処理法の施行状況を検討し、必要に応じて同法を見直すこととなっています。そして、平成29年改正のマニフェストに関する部分の施行が令和7年をもって見当が始められています。6月24日には、見直しの中間とりまとめが公表されました。
中間とりまとめを見る前に、平成29年改正に先立って意見具申された「廃棄物処理制度の見直しの方向性」と平成29年改正法を検証したいと思います。
平成29年改正
⑴「許可を取り消された業者が廃棄物処理を終了していない場合に自治体が必要な措置を命令可能に」
とは
改正前は、措置命令の対象に処理業者ではなくなった者が含まれていませんでした。そのため許可を取り消され処理業者でなくなった者に対しても措置命令を行う根拠条文を整備しました。
⑵マニフェスト制度の強化
①マニフェスト規制違反の厳罰化
改正前は6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されていました。しかしダイコー事件においてダイコー社が電子マニフェストによる虚偽報告を行っていたことなどが問題視され、マニフェスト規制違反が厳罰化されました。改正後は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
②多量排出事業者に対する電子マニフェストの使用の義務付け
電子マニフェストは不適正処理の未然防止や処理過程の透明性向上を図ることが期待できる一方、普及率は45%となっていました。そこで特別管理産業廃棄物処理業者で、当該年度の前々年度において産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者に対し、電子マニフェストの使用を義務付けることとしたものです。
⑶有害使用済み機器の処分業者に対する届出の義務化
現在、有害使用済み機器の保管または処分を行う者に対しては、管轄の都道府県知事に届出を行う義務が課され、かつ、有害使用済み機器に関する保管および処分についての基準が設けられています。また有害使用済み機器の保管業者または処分業者は、都道府県による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令の対象となります。有害使用済み機器は、有害性があっても廃棄物ではないので、本来は廃棄物処理法の対象となりません。しかし環境保全の観点から特別に廃棄物処理法の規制対象となりました。
⑷親子会社による一体的処理の特例
親子会社の一方の産業廃棄物を処理するためには、産業廃棄物処理業の許可が必要となるのが原則です。しかし近年、企業経営の効率化の観点から分社化等が増加し、従来は「自ら処理」ができなくなる事態が発生していたことが問題視されていました。そこで親子会社が一体的な経営を行うものであると都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理が可能となりました。
次回はこの中間とりまとめについてみていきたいと思います。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
