INDUST2018年6月号に「M&A・組織再編と廃棄物処理法」が掲載されました
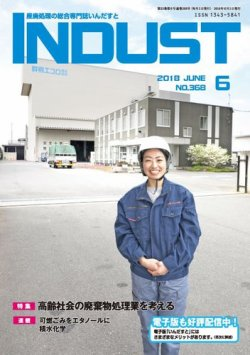
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年6月号に「M&A・組織再編と廃棄物処理法」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1680990/
今回は、M&A・組織再編にあたり廃棄物処理法の観点から注意すべき事項をご紹介したいと思います。
M&A・組織再編と許認可
M&Aには多種多様な方法があります。2社以上の会社が組織再編を行う手法として、大きく分けると【吸収型】の手続きと、【新設型】の手続きがあります。そして、「事業許可」は、法人格単位で与えられるものであるので、法人格の同一性が失われた場合、事業許可は小計されないことになります。
例えばA社がB社の株式を取得する株式譲渡の場合、B社からみると株主が交代するだけであり、B社の組織としては変更がありません。そのためB社の事業許可は影響を受けません。一方で、A社がB社の権利義務のすべてを取得する吸収合併の場合、B社は消滅してしまいます。そのためB社の事業許可はA社に承継されません。さらに、B社がA社に事業の一部又は全部を譲渡する会社分割の場合、分割されたB社は存続します。そのため許認可の移動は生じません。会社分割で事業を譲り受けても、それに伴う許認可の承継はできないことに注意する必要があります。
施設設置許可についての特例
廃棄物処理法は、「施設の設置許可」については、特例を設けています。具体的には、吸収合併または会社分割により廃棄物処理施設が承継され、都道府県知事の認可を受けたときは、「施設の設置許可」も承継されるとされています。この認可については、「施設の維持管理を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして環境省例で定める基準に適合するものであること及び欠格要件に該当しないこと」が要件とされていますので、その審査に関する負担は決して軽くないというのが実情のようです。
かつては「自社」で廃棄物を処理していると言うためには、同処理業務にあたる人員は「自社」と直接の雇用関係がある者である必要があると捉えられてきました。しかし、このような基準では、雇用の流動化が生じている現実にそぐわないものとなっていました。そこで平成17年3月25日付環境省通知は、「自ら処理」について、一定の要件を設けて、廃棄物処理業務に従事できる者を拡張しています。
⑴当該事業者がその産業廃棄物の処理について自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていること。
⑵処理の用に供する処理施設の使用権原及び維持管理の責任が、当該事業者にあること。
⑶当該事業者が業務従事者に対し、個別の指揮監督権を有し、業務従事者を雇用する者との間で業務従事者が従事する業務の内容を明確かつ詳細に取り決めること。またこれにより、当該事業者が適正な廃棄物処理に支障を来すと認める場合には業務従事者の変更を行うことができること。
⑷当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で、法に定める排出事業者に係る責任が当該事業者に帰することが明確にされていること。
⑸⑶と⑷の事項が、当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で労働者派遣契約等の契約を書面にて締結することにより明確にされていること。
親子会社の特例
排出事業者に関する特例になりますが、平成29年法改正により、親子会社であって、子会社が親会社の一部門のような関係にある場合には、両会社を一体の排出事業者として扱う旨の特例が新設されました。「一体的な経営を行っている」という要件について、①完全子会社、または②議決権株式の2/3を保有し、役員を派遣したうえで、以前は両法人が同一の事業者であったことが求められています。さらに「適正処理を行う能力を有していること」も要件として挙げられており、それを示す書類を提出したうえで、都道府県の認定を受けなければなりません。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
