INDUST2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました
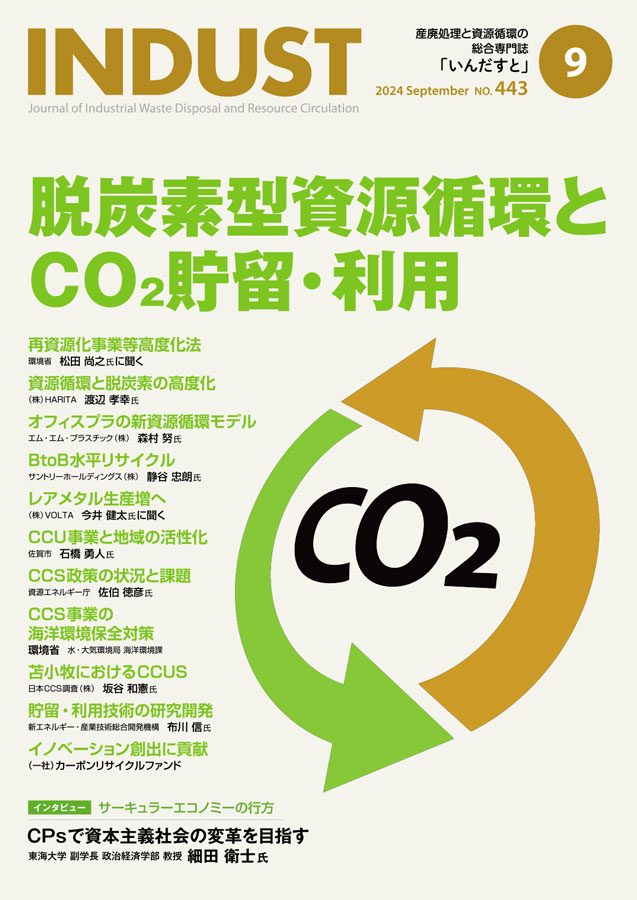
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2567367/
近時、「砂押プラリ事件」という興味深い事件がありました。
砂押プラリ事件とは、砂押プラリ株式会社(以下、「砂押プラリ社」といいます。)が営業範囲の無許可変更を行ったことを理由に許可が取り消された事件です。同事件では、未処理の感染性廃棄物が大量に残されており、それらの処分をどのようにするかも問題となっています。砂押プラリ事件の概要を知るとともに、なぜこのような事態が生じてしまったのか、処理業者、排出事業者として何かできるか検討したいと思います。
1 感染性廃棄物と医療廃棄物の関係
廃棄物処理法上の分類ではありませんが、医療的性質を有する廃棄物全般は医療廃棄物と呼ばれています。本件の感染性廃棄物とは、医療系で、かつ、感染性を有する廃棄物、ということになります。
2 医療系感染性廃棄物の処理方法
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和4年6月)(環境省)によれば、以下の方法が認められています。
①焼却設備を用いて焼却する方法
②溶融設備を用いて溶融する方法
③高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)
④乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法(さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)
⑤消毒する方法(肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法とし、さらに破砕する等滅菌したことを明らかにすること。)
3 砂押プラリ社の処理方法(滅菌)は適切だったのか
砂押プラリ社が許可を受けていたのは、「滅菌」です。滅菌後の医療廃棄物のリサイクルをうたっていたとのことです。滅菌処理方法として想定されるのは、高圧蒸気機滅菌か乾熱滅菌です。高温に耐えられることがいずれの処理方法にも必要であるとされています。たとえば、メスやシャーレは高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌ともに適切であると考えられますが、砂押プラリ社が処理の委託を受けていたという血液や臓器等は、「滅菌」をすることがそもそも想定しえません。
また、許可取消処分の理由は、「許可を受けた滅菌処理以外の方法により処理を行った」というものですが、滅菌以外のどのような処理を行ったのか明らかにされていません。むしろ、「処理を行わなかった」というべきで、実態は不法投棄ではないかという疑問が残ります。
4 許可取消処分とその後
⑴ 宮城県による措置命令
宮城県は、令和5年(2023年)10月23日、砂押プラリ社の許可取消処分を行いました。
その後保管容量を超えた廃棄物を保管容量の上限に至るまで減少せよ、という内容の措置命令を発出しています。また、砂押プラリ社による撤去が事実上不可能であるため、排出事業者である病院等に撤去を求めているとされています。
⑵ 検討
ア 措置命令の内容
同社に対する取消処分は事業範囲の無許可変更を理由とするものであり、保管容量すべてを不法投棄であると認定するものではないため、全量撤去を命じるのではなく、保管容量の上限まで撤去を命じたものと推測することができます。
イ 減少命令は適切か
① 一部残置させる法的根拠がないのでは?
廃棄物の「保管」は廃棄物処理業の許可に伴って認められるものであり、「保管」という独立の許可があるわけではありません。許可が取り消された以上、廃棄物の保管の根拠がなくなるわけですから、許可があることを前提とする保管廃棄物についても撤去を命じられるべきではないでしょうか。
② 廃棄物の「飛散、流出のおそれ」は残置された廃棄物にもあるのでは?
宮城県は、措置命令の根拠として、「当該廃棄物の一部は、経年劣化により保管容器が一部破損した状態で野外に野積みされているため、当該廃棄物に浸透した雨水が地下浸透するおそれがあるほか、当該廃棄物自体が飛散、流出するおそれがある」ことをあげています(「4 命令を行う理由」⑵)。
これを根拠とするのであれば、野外に野積みされた廃棄物は全量撤去されるべきで、保管容量の範囲で野積みが許容されるべきではありません。
ウ 排出事業者に対する措置要請
排出事業者は廃棄物が不適正に処理され、放置されていた場合に常に法的に責任を負うわけではありません。排出事業者に委託基準違反またはマニフェスト規制義務違反等の具体的な法令違反がある場合(法第19条の5第1項)、もしくは以下の要件を満たされた場合には措置義務を負うことになります(法第19条の6第1項)。
①廃棄物が不適正に処理され、②残置された廃棄物により生活環境保全上の支障が生じ、または生じるおそれがあると認められる場合であること、③処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等によっては支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、または講じても十分でないとき、④排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたとき
現在のところ、排出事業者の具体的法令違反があることまでは認定されておらず、それゆえ撤去要請(行政指導)がされていると思われます。排出事業者による撤去が進まなかった場合、今後、県としては、排出事業者の責任を認定し、排出事業者に対して措置命令を行う可能性があります。
これに対しては、排出事業者から、県は砂押プラリ社が保管容量を超えて保管していることを長年にわたり放置しており、県に監督義務違反があり、排出事業者に対して責任を転嫁するのは不当であるとの声がすでにあがっています。
なお、中間処理業者も処理後物の処理を委託する場合には、その処理後物について排出事業者となることに留意してください。
本稿ではより詳しく解説していきます。
ぜひご覧ください。
