INDUST10月号に「排出事業者責任と措置命令 その2」が掲載されました
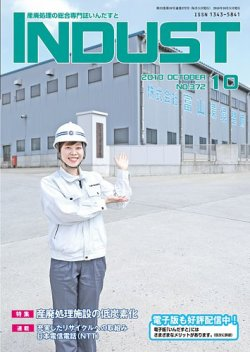
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年10月号に「排出事業者責任と措置命令 その2」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1733047/
前回から引き続き、排出事業者は排出事業者責任を負っていることを前提に、措置義務を追及されないために何をすべきかをご紹介しています。今回は、排出事業者が措置義務を追及されないために契約締結後に確認すべきこと、措置義務に関して注目されるキンキクリーンセンター判決等についてご紹介したいと思います。
措置義務を免れるために排出事業者は契約締結後に何をすべきでしょうか。
まず排出時には、廃棄物処理法に基づきマニフェストを交付する必要があります。このマニフェスト制度は、廃棄物と共に移転し、各処理工程完了ごとに排出事業者へ返送されることで、処理状況を把握し、問題発生時に必要な措置をとることを可能にするシステムです。
排出後は、マニフェストの返送確認と保存が重要です。収集運搬・中間処理については10日以内、最終処分については180日以内に返送されるべきであり、期間内に返送がない場合は処理状況を確認し、適切な措置をとる必要があります。適切な措置とは、他の処理業者への委託変更や、問題のある処理業者への委託停止などが含まれます。
また現地確認による処理状況の確認も欠かせません。処理施設が適正に運営されているか、廃棄物の保管状況は適切か、自社の廃棄物排出量と処理業者の処理能力のバランスはとれているかを確認すべきです。特にリサイクル処理の場合は、最終的な販売先や販売価格、契約書の確認まで行うことが理想的です。食品廃棄物処理の例では、堆肥化後の製品が適切に販売されているかの確認が重要です。ダイコー事件のようにマニフェストが偽造されるケースもあり、定期的な現地確認と具体的なチェックリストの作成が必要です。不適正処理を防ぐためには、リサイクル製品の販売状況や価格の合理性まで確認することが求められます。
2017年のキンキクリーンセンター事件判決は、排出事業者責任の観点から注目すべきものでした。この事件では、処分場の許容量を大幅に超える廃棄物が搬入され、福井県と敦賀市が撤去費用を負担した後、敦賀市が他の自治体に費用負担を求めた訴訟です。判決では、市町村は一般廃棄物処理について「支障除去等の包括的措置義務」を負うとし、処理を委託した場合や他の自治体に持ち込まれた場合でもその責任は失われないとしました。
この判決は生活環境保全と公衆衛生向上という観点から理解できる面がありますが、判決中で産業廃棄物の排出事業者にも同様の「包括的措置義務」があるとした点には疑問が残ります。自治体と異なり、産業廃棄物の排出事業者には委託基準遵守やマニフェスト管理など法定義務があり、これらを果たしていても不適正処理が行われた場合に「包括的措置義務」が免れないとすれば、法の定める排出事業者責任との整合性に課題が生じます。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
