INDUST12月号に「『逆有償』と大同特殊鋼事件」が掲載されました
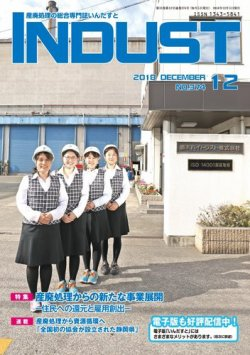
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年12月号に「『逆有償』と大同特殊鋼事件」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1755859/
今回は、排出事業者責任の観点から大きな注目を集めた大同特殊鋼事件をご紹介します。
2013年に、群馬県渋川市の遊園地駐車場改修時に大同特殊鋼が出荷した鉄鋼スラグから基準値を超える六価クロムとフッ素が検出されました。その後の調査により、鉄鋼スラグとは、鉄鋼製造工程で発生する副産物です。通常は有価物としてセメント原料や道路舗装用素材などに再利用されます。同社が出荷した鉄鋼スラグは公共工事で計56工事、225カ所で使用され、96カ所で環境基準値を超えるフッ素や六価クロムが検出されました。
群馬県は、2015年9月7日、①大同特殊鋼、②大同特殊鋼より同社の鉄鋼スラグを「購入」し、佐藤建設工業に「売却」していた大同エコメット、③大同エコメットより大同特殊鋼の鉄鋼スラグを「購入」し、建設業者に同鉄鋼スラグを「売却」していた佐藤建設工業の3社を廃棄物処理法違反を理由に刑事告発しました。しかし2016年12月に群馬地検は大同特殊鋼ら3社を「嫌疑不十分」で不起訴としました。
本件の場合、鉄鋼スラグの売買が行われた一方、大同特殊鋼から大同エコメットに対しては「エージング費用」として、また、大同特殊鋼から佐藤建設工業に対しては「販売管理費」という名目で売買代金以上の金額が支払われていました。このように、売買代金として受け取った以上の金額を何らかの名目によって売買契約の相手方に支払うことを「逆有償」といいます。
ある物が廃棄物に当たるかどうかは、「総合判断説」によって判断されます。「総合判断説」とは、「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべき」とする考え方です。
各要素を総合的に勘案して、本件鉄鋼スラグは「廃棄物」であることが強く疑われますが、群馬地検は、大同特殊鋼ら3社を「嫌疑不十分」で不起訴としました。「嫌疑不十分」とは、起訴をして「有罪判決を得るための証拠が不十分」であるという意味であり、「無罪」という意味ではありません。どのような証拠が他に必要だったのか、どのような判断で不起訴となったのか非常に興味のあるところです。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
