INDUST2018年2月号に「漂着した木造船はどうやって廃棄する」が掲載されました
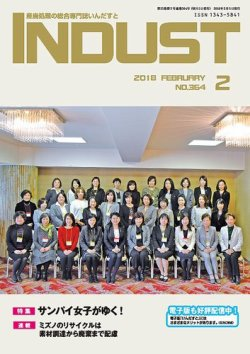
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年2月号に「漂着した木造船はどうやって廃棄する」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1624465/
昨年、日本海沿岸に多数の北朝鮮船籍とみられる木造船が漂流・漂着しています。報道によると、これら木造船は最終的には廃棄物として処理することになる可能性が高いようですが、いったい誰がどのようにして処理をするのでしょうか。今回は、このニュースについて廃棄物処理法の観点から見ていくことにします。
廃棄物処理法は、「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち20種類を「産業廃棄物」として定義し、その定義に当てはまらないものはすべて「一般廃棄物」であるとしています。木造船はいったい誰が排出したのかが分かりませんから、「事業活動に伴って生じた廃棄物」ということはできません。そのため木造船は産業廃棄物には該当せず、一般廃棄物として処理するのが法的には正しいということになります。
そのため最終的には市町村の一般廃棄物処理施設において処理することになります。しかし多くの市町村の一般廃棄物処理施設においては、家庭から出る小さな「木くず」の処理のみを行っており、木造船のようなイレギュラーな大きさのものについては、搬入することは難しいことが多いように危惧されます。
このような問題は、そもそも廃棄物処理法が、廃棄物の形や大きさではなく、業種等により廃棄物の種類を決めているにもかかわらず、実際の処理の現場ではやはり形状・大きさ等により処理の方法が変わってしまうことから生じています。これについては再検討する必要があると考えています。
以前から、海岸に漂着する「海岸漂着物」の処理については重大な問題として議論されており、平成21年に「海岸漂着物処理推進法」が制定されました。同法においては、海岸法等により指定された海岸管理者が「海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない」とされています。これにより、海岸の清掃事業については都道府県と市町村が中心となって行う体制になっています。
そのため木造船も都道府県と市町村が費用負担を行って処理することになります。木造船の処理費用は1隻辺り150~200万円ほどにのぼるという報道もされており、軽視できる負担ではありません。そこで政府は昨年12月下旬以降、海上保安庁が朝鮮半島から来たと確認した船については、処理費の全額を負担する方針を打ち出しています。
漂着した木造船について、「所有者が不明な財産」として扱うべきなのではないかという問題について、木造船の所有者が名乗り出ることはほとんど考えられません。しかし船としての形態と機能がある限り、即座に廃棄物とすることは難しいと思われます。このような漂流物は、水難救護法において、市町村が保管・公告をしなければならないと規定されています。これにも負担が生じるため、木造船については所有者が判明しない不要物であることを緩やかに認定していくほかないと思われます。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
