INDUST2018年5月号に「有害使用済機器」が掲載されました
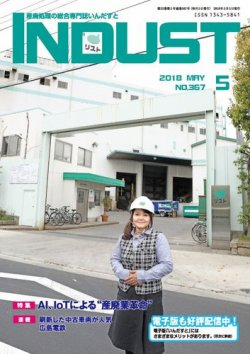
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年5月号に「有害使用済機器」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1664519/
本年4月より、平成29年法改正が施行され、有害使用済機器の保管等に関するガイドラインが本都市3月に環境省ホームページにおいて公表されました。今回は、この「有害使用済機器」の規制について改めて見ていきたいと思います。
環境省によると、「使用済電子機器と金属スクラップ等が混合された物(雑品スクラップ)が、環境保全措置が十分に講じられないまま、破砕や保管されることにより、火災を含む生活環境保全上の支障が発生しており、対応の強化が必要となっている」とされています。このような背景から新たに条項が新設され、具体的な基準や適用範囲を定めた政省令も整備されています。今回の法改正のポイントは、「有害使用済機器」は有価物であることが前提となっている点です。改正法は、物の性質上これを扱う業者に届出を義務付け、廃棄物処理業者が負うような保管基準・処分基準を課し、報告徴収や立ち入り検査、改善命令等の対象とする内容になっています。
規制対象は、「有害使用済機器」の処理・保管業者であり、対象品目は、32品目になります。これらは家電リサイクル法の対象4品目と小型家電リサイクル法の対象28品目が規定されています。
規制の対象者は、有害使用済機器の保管と処分を行う事業者です。同機器の収集・運搬業者と排出事業者は、今回の規制では対象外となっています。また廃棄物処分業者(一廃・産廃)、積替保管を行う廃棄物収集運搬業者(一廃・産廃)についても、対象外となっています。その他にも対象外となる事業者も多く列挙されています。
有害使用済機器保管等業者は、保管等を開始する10日前までに、都道府県知事又は政令市長に対して、届出を行う必要があります。なお、この届出については本年(平成30年)10月1日まで猶予されています。
保管基準・処分基準については、「囲いの設置」、「掲示板の設置」、「保管の高さ規制」、「土壌・地下水汚染防止」等について定められており、概ね廃棄物の保管基準等に近い規制がなされています。
また廃棄物処理業者と同様ですが、帳簿の作成・保管義務、さらに行政による調査や命令に服する義務を負うことになります。さらに、法改正により規制を新設した以上、その強制力の確保のために罰則も規定されることになりました。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
