INDUST2024年5月号に「行政手続と廃棄物処理法 その9 ~不許可処分取消請求(認容事例2)(平成21年8月27日東京高裁判決)~」が掲載されました
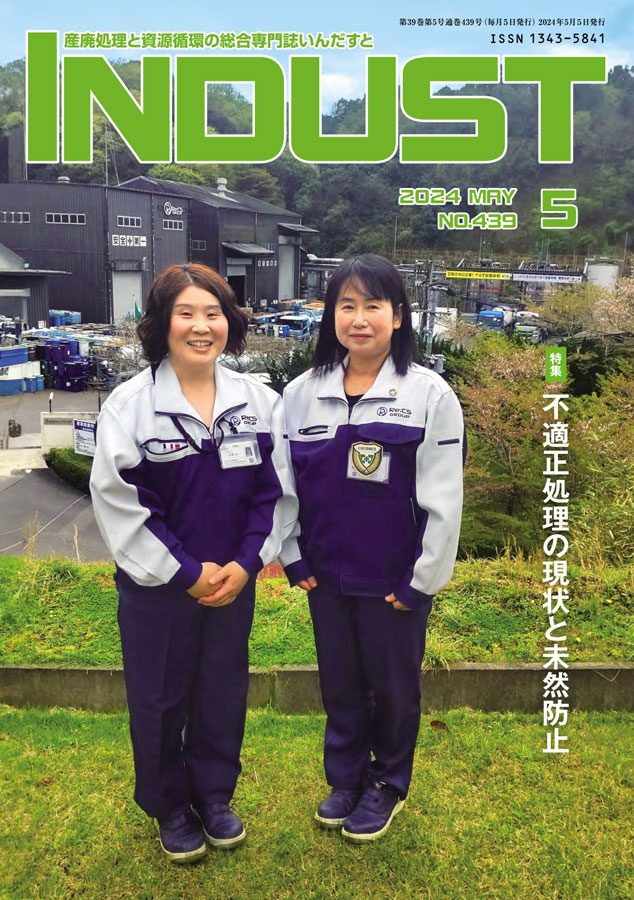
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年5月号に、「行政手続きと廃棄物処理法 その9 〜不許可処分取消請求(認容事例2)〜(平成21年8月27日東京高裁判決)」が掲載されました。
zensanpairen.or.jp/books/indust/15008/
今回取り上げるのは、平成21年8月27日の東京高裁判決で、許可取消処分の違法性が認められた事例です。この判決は行政処分のあり方について詳細な分析がなされており、実務上の参考になる重要な判決といえます。
事案の概要は、下水汚泥等から汚泥発酵肥料を生産しているX社が、ある畑に「肥料」を搬入した行為について、県がこれを不法投棄と認定し、X社の許可を取り消したというものです。これに対してX社は当該許可取消処分の違法性を主張し、取消しを求めて訴えを提起しました。一審ではX社の請求は認められませんでしたが、東京高裁ではX社の主張が認められ、許可取消処分は違法であるとして取り消されました。
争点は、畑に搬入された「肥料」が「廃棄物」に該当するかどうかでした。県は、搬入物には生理用品、プラスチック片、木くず片等の異物が混入しているため適正な「肥料」とは認められず「廃棄物」である、と主張しました。これに対してX社は、異物の混入はわずかであり肥料としての効能に影響を与えるものではないから「廃棄物」ではない、と反論しました。
東京高裁は、まず本件のような取消訴訟においては、処分要件の存在について立証責任は県側にあると明確にしました。すなわち、県はX社が運び込んだ物が「廃棄物」に当たり、これを運び込んだ行為が廃棄物を「みだりに捨てた」ことに当たることを立証しなければならず、この立証が十分でなければ許可取消処分は取り消されるべきとしました。
「廃棄物」該当性の判断において、裁判所は物の性状、排出状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合的に検討しました。その中で、物の性状については、本件搬入物自体が保存されておらず、分析結果も残されていないという県側の証拠収集の不備を指摘しました。異物の混入についても、搬入から3ヶ月以上後に収集された異物の量はわずかであり、混入率は重量にして0.000065%にすぎないとして、これをもって「廃棄物」と認定することは困難とされました。
また、施肥量が過大であったかという排出状況や、肥料としての市場性、取引価値の有無についても、廃棄物と断定するには疑問が残るとし、結論として「みだりに廃棄物を投棄したものとして、廃棄物処理法16条に違反するとの証明は不十分」と判断しました。
この判決から学ぶべき点は、行政が処分を行う際の証拠収集のあり方です。裁判所は随所で行政処分のあり方を批判しており、例えば「廃棄物」と認定するならばサンプルを保存すべきであること、搬入から9ヶ月後のサンプル調査では不十分であること、異物混入を根拠とするならば搬入後速やかに調査すべきことなどを指摘しています。
行政処分を行う際には、処分の根拠となる事実を客観的かつ迅速に証拠化し、保存することが不可欠です。特に、物の性状が変化しうる事案では、速やかな調査と証拠保全が求められます。この判決は、行政側が廃棄物該当性を立証するために必要な手続きと、事業者側が行政処分の違法性を主張する際の着眼点を示す重要な先例といえるでしょう。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
