INDUST7月号に「欠格要件制度の現状と対策」が掲載されました。
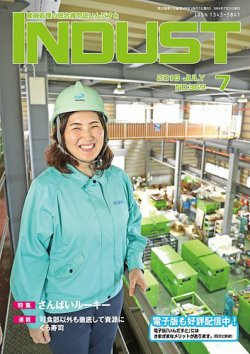
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年7月号に「欠格要件制度の現状と対策」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1693862/
今回は、累次の改正により分かりにくくなった欠格要件制度の現状を確認するとともに、欠格要件制度の課題と今後の方向性、欠格要件制度から企業を守る対策を検討したいと思います。
欠格要件制度は法が定める一定の要件に該当する場合に許可を与えない、あるいは取り消す仕組みです。適正な業務遂行が期待できない者を排除する目的がありますが、平成22年の法改正までは規制が厳しくなり、その後一部緩和されています。
具体的な問題点として、株式の10%を保有する株主が成年被後見人になった場合、その株主が「みなし役員」として扱われ、会社の許可が取り消されるケースがあります。また、役員が業務と無関係の暴行罪や道路交通法違反で罰金刑や禁錮刑を受けた場合でも、同様の事態が生じます。
平成22年の法改正により、欠格要件の「連鎖」については一定の制限が設けられました。以前は役員を共通にする関連会社にも無限に波及していましたが、現在は廃棄物処理法違反など悪質性の高い場合に限定されています。しかし、「みなし役員」の範囲が不明確である点や、業務と無関係の理由で許可が取り消される硬直的な運用は、なお課題として残っています。
企業を守るための対策としては、株式の分散防止・集約とホールディングス化が有効です。株式については、5%以上の株式保有者が「みなし役員」とされる可能性があるため、株主を把握し、管理の届かない株主からは株式を買い取るなどして集約することが重要です。また、複数の関連会社がある場合は、株式保有のみを目的とするホールディングス会社を設立することで、一社が欠格要件に該当しても他社への連鎖を防ぐことができます。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
