INDUST2024年8月号に「両罰規定と廃棄物処理法」が掲載されました
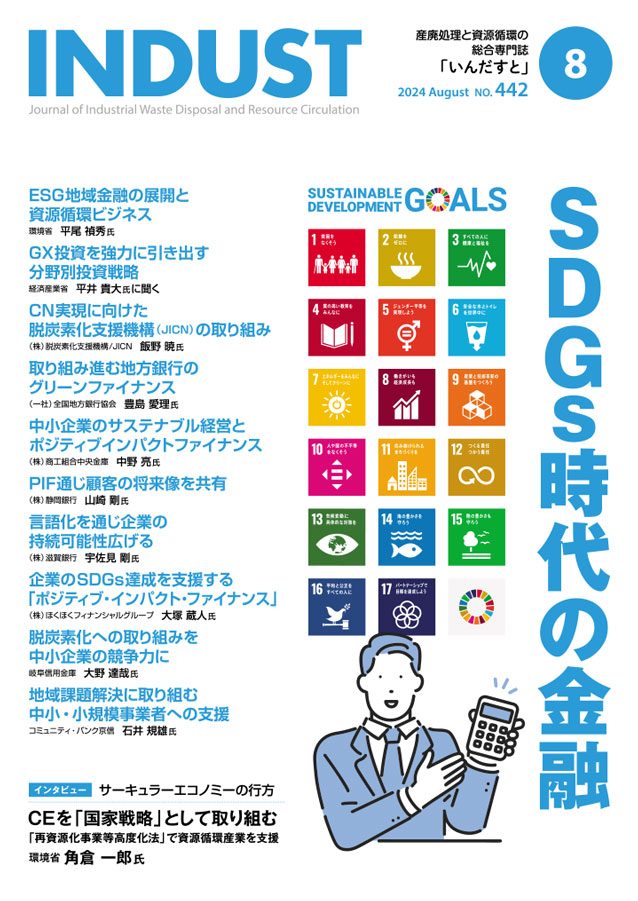
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年8月号に「両罰規定と廃棄物処理法」が掲載されました。
zensanpairen.or.jp/books/indust/16061/
今回は両罰規定について解説します。両罰規定とは、会社の役員・従業員等が違法行為を行った場合に、「従業員と会社を両方処罰する」という規定です。
両罰規定の趣旨は、従業員の違法行為によって利益を得ようとする会社の行為を防止することにあります。刑事罰は通常、違法行為を行った個人に対してのみ適用されますが、例えば従業員が会社の指示で不法投棄を繰り返し、会社がその結果として処理費用相当の利益を得ている場合、従業員だけを処罰しても根本的な解決にはなりません。そこで廃棄物処理法第32条第1項は、従業員が業務に関して違法行為を行った場合に会社も処罰するとしています。
両罰規定が適用される要件は次の3点です。①法人の代表者や従業員等が廃棄物処理法違反をした場合であること、②その違反が法人の「業務に関して」行われたこと、③その従業員等が処罰される場合であること。です。
特に「業務に関して」の解釈が重要です。判例は「当該行為が一般的、外形的に事業主の業務に属すること」と広く解しており、例えばドライバーが会社の指示に反して河川敷に廃棄物を不法投棄した場合でも、「業務に関して」行われたと認定される可能性が高いのです。
両罰規定の法的性質については、会社の従業員に対する選任・監督上の過失が処罰根拠とされていますが、この過失の立証責任については見解が分かれています。刑事手続の原則からすれば検察官が立証すべきですが(具体的過失説)、判例は両罰規定を「過失推定規定」と解しており、会社側が「過失がなかった」ことを証明しない限り責任を免れないとしています(過失推定説)。しかし、廃棄物処理法においては両罰規定の適用が特に重大な結果をもたらします。一従業員の違法行為により会社が罰金刑を科せられると、廃棄物処理法上の欠格要件に該当し、許可が取り消されてしまうからです。これは他の法律(外為法や入場税法など)とは異なる廃棄物処理法特有の厳しい帰結です。
会社が両罰規定の適用を避けるための予防策として最も重要なのは、廃棄物処理法に関する社員教育の実施と、その記録の保存です。また、従業員が違法行為を行ったことが発覚した場合には、直ちに弁護士に相談し、捜査機関への対応や検察官との交渉など適切な対策を講じることが不可欠です。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
