INDUST2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました
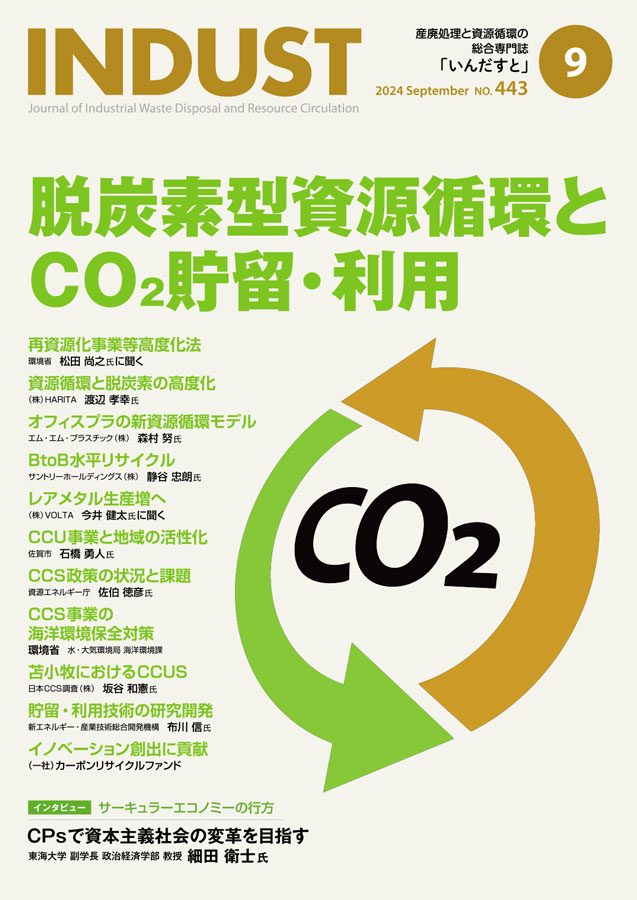
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年9月号に「『砂押プラリ事件』を考える」が掲載されました。zensanpairen.or.jp/books/indust/16318/
今回は、近時注目を集めている「砂押プラリ事件」について法的観点から考察します。この事件は、宮城県内で感染性廃棄物の中間処理を行っていた砂押プラリ株式会社が営業範囲の無許可変更を理由に許可を取り消された事案です。
砂押プラリ社は宮城県から特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けて感染性廃棄物の中間処理を営んでいましたが、2019年4月から2023年3月までの間に病院等から中間処理を受託した液体状の感染性廃棄物約200㎥について、許可を受けた「滅菌処理以外の方法」により処理を行った疑いがあるとして、廃棄物処理法第14条の5第1項違反(無許可変更)を理由に許可取消処分を受けました。さらに問題なのは、未処理の感染性廃棄物が大量に残されており、それらの処分をどうするかという点です。
まず、感染性廃棄物と医療廃棄物の関係について整理しておきます。医療廃棄物とは廃棄物処理法上の分類ではありませんが、医療機関から排出された廃棄物等、医療的性質を有する廃棄物全般を指します。本件で問題となっている感染性廃棄物は、医療系で感染性を有する廃棄物です。環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」によれば、感染性廃棄物の処理方法として、①焼却、②溶融、③高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)、④乾熱滅菌、⑤消毒が認められています。砂押プラリ社が許可を受けていたのは「滅菌」です。滅菌とは「あらゆる微生物を完全に殺滅または除去する状態を実現するための作用・操作」を意味します。
ところが、砂押プラリ社は医療系感染性廃棄物のうち血液や臓器等の処理も委託を受けていたとのことです。こうした廃棄物は「滅菌」に適さないものです。滅菌処理方法として想定される高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌は、ガラス製の器具や金属製器具、紙製品などには適していますが、血液や臓器等の滅菌は想定し得ません。また、感染性廃棄物を入れるプラスチック製の密閉容器は、蓋を開けることなく密閉性を保ったまま焼却されるべきもので、高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌にはそぐわないものです。
許可取消処分の理由は「許可を受けた滅菌処理以外の方法により処理を行った」というものですが、実際にはどのような処理が行われたのか明らかになっていません。むしろ「処理を行わなかった」と考えるべきで、実態は不法投棄に近いのではないかという疑問が残ります。
宮城県は2023年10月に砂押プラリ社の許可を取り消した後、2024年3月に措置命令を発出しました。この命令は、中間処理施設の保管容量(364㎥)を超えて保管している廃棄物を364㎥以下になるまで減少させよというものです。しかし、この措置命令には疑問が残ります。まず、同社はすでに許可取消処分を受けており、廃棄物を保管すること自体ができない状態です。廃棄物の「保管」は廃棄物処理業の許可に伴って認められるものであり、許可が取り消された以上、保管の根拠がなくなるため、364㎥も含めた全量撤去を命じるべきではないでしょうか。
また、宮城県は措置命令の根拠として、廃棄物の「飛散、流出のおそれ」を挙げています。野積みされた廃棄物からの雨水の地下浸透や廃棄物自体の飛散・流出のおそれがあるのであれば、野積みされた廃棄物は少なくとも全量撤去されるべきで、364㎥の範囲内で野積みが許容されるべきではありません。
砂押プラリ社による撤去が事実上不可能であることから、宮城県は排出事業者である病院等に撤去を要請しています。この要請の根拠は排出事業者責任(法第3条第1項)です。排出事業者は自ら排出した廃棄物について、適正に処理を委託した後も、マニフェスト等により最終処分完了まで管理監督する義務があり、適正に処理されていない場合には自らの責任で処理しなければなりません。
ただし、排出事業者が常に法的責任を負うわけではありません。委託基準違反やマニフェスト規制義務違反等の具体的法令違反がある場合、または具体的法令違反がなくても一定の要件(生活環境保全上の支障があり、処分者の資力等から支障除去措置が困難で、排出事業者が適正な対価を負担していない等)を満たす場合に限り措置義務を負います。
現在のところ、排出事業者の具体的法令違反は認定されておらず、撤去は「要請」(行政指導)段階にとどまっています。しかし今後、排出事業者による撤去が進まなければ、県は排出事業者の責任を認定し、措置命令を行う可能性があります。これに対し排出事業者からは、県が砂押プラリ社の保管容量超過を長年放置してきたという監督義務違反を指摘し、責任転嫁は不当であるとの声が上がっています。
この事件は、廃棄物処理業の許可内容と実態の乖離、行政の監督責任、排出事業者責任の範囲など、廃棄物処理における複雑な法的問題を浮き彫りにしています。処理業者、排出事業者、行政それぞれが適切に責任を果たすことの重要性を改めて考えさせる事例です。
なお、中間処理業者も処理後物の処理を委託する場合には、その処理後物について排出事業者となることに留意してください。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
