INDUST9月号に「排出事業者責任と措置命令」が掲載されました。
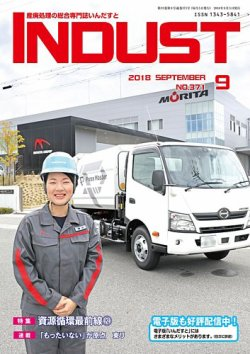
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年9月号に「排出事業者責任と措置命令」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1718688/
今回は、近時重要度、注目度を増している排出事業者の措置義務についてみていきたいと思います。
廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という基本原則が定められており、処理を他者に委託した場合でも、発生から最終処分まで一連の処理過程における責任は排出事業者にあります。この「排出事業者処理責任の原則」を具体化するため、法律は委託基準の遵守、マニフェストの交付・確認・保存、処理状況の把握と適切な措置義務などを定めています。
排出事業者が措置義務を免れるためには、契約締結前に許可業者であることの確認や現地訪問による実態把握、契約後にはマニフェスト管理と返送確認、定期的な処理施設の視察が重要です。特に食品廃棄物などのリサイクル処理では、マニフェスト偽造のリスクもあるため、処理状況と販売先・価格の合理性まで確認することが必要とされています。
2017年のキンキクリーンセンター事件判決は、排出事業者責任の観点から重要な判断を示しました。この判決では、自治体は一般廃棄物処理について「支障除去等の包括的措置義務」を負うとし、処理を委託した場合や廃棄物が他の自治体に持ち込まれた場合でもその責任は継続するとしました。一方で、産業廃棄物の排出事業者にも同様の義務があるとした点には疑問が提起されています。排出事業者が法定の責任を果たしていても不適正処理が行われた場合の責任範囲については、法の趣旨との整合性に課題があるという指摘もあり、今後も議論が続くと考えられます。
近年、環境省通知により排出事業者責任の重要性が改めて注意喚起されており、排出事業者は廃棄物処理の全過程における責任を認識し、適切な対応を取ることが一層求められています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
