INDUST 2024年11月号に「契約書作成の基本とポイント」が掲載されました
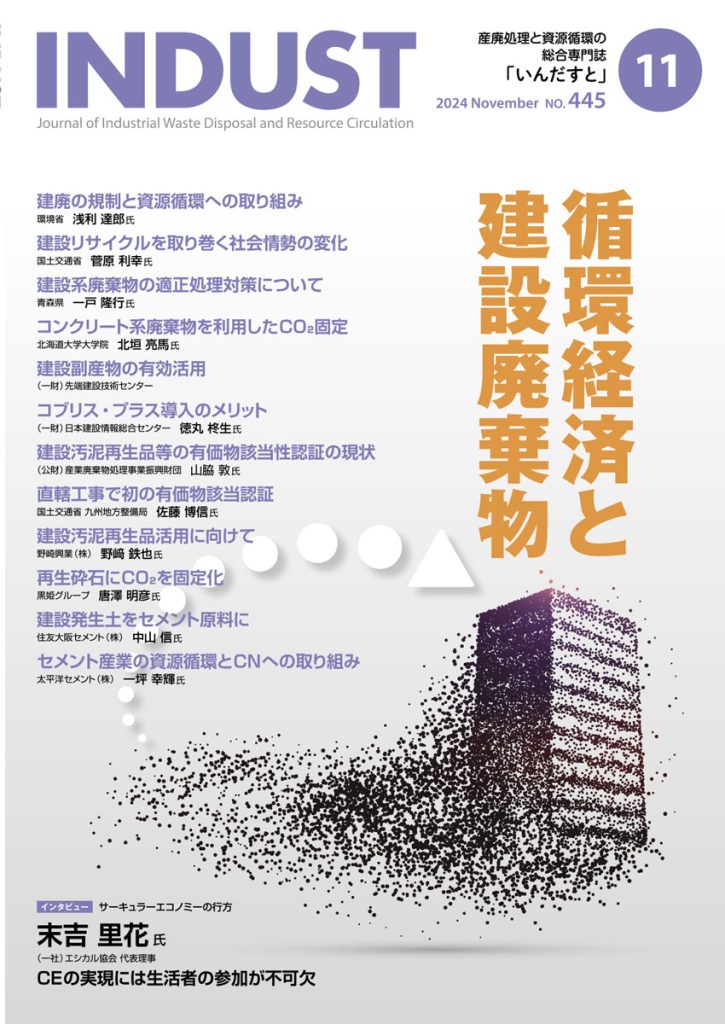
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年11月号に「契約書作成の基本とポイント」が掲載されました。
zensanpairen.or.jp/books/indust/19687/
今回は廃棄物処理委託契約書作成の基本とポイントについて解説します。廃棄物処理委託契約書は廃棄物処理取引のスタートであり、取引上も法的責任の面でも極めて重要なものです。弊所での相談項目でも常に上位に位置する問題です。
産業廃棄物処理委託契約書の作成は排出事業者の法的責任です。排出事業者は産業廃棄物の収集運搬または処分を委託する際、政令で定める委託基準に従わなければならず(廃棄物処理法第12条第6項)、その一つとして契約書作成が義務付けられています(同法施行令第6条第4号)。さらに契約書には法定の必要的記載事項をすべて記載しなければなりません。
もし契約書が作成されない場合や必要的記載事項が一つでも欠ける場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科される重い罰則が設けられています(法第26条第1号)。
なぜこのように厳格な義務が課されているのでしょうか。一般的な民事契約では契約自由の原則により、契約を締結するかどうか、どのような内容の契約にするか、契約書を作成するかどうかは当事者の自由です。一般廃棄物についても契約書作成義務はありません。
しかし産業廃棄物処理については、排出事業者責任の原則に基づき、適正処理確保のために厳格な規制が設けられています。排出事業者責任とは「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(法第3条第1項)という責任であり、環境負荷の原因を作った者がその責任において適正に処理すべきという汚染者負担の原則に由来します。
具体的には、①自ら処理する場合は処理基準を遵守する義務、②他人に委託する場合は適正な業者に適正に委託する義務(委託基準遵守義務)、③委託後もマニフェスト管理等を通じて最終処分完了まで追跡・管理監督する義務があります。産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者がこの責任を全うするための第一歩なのです。
また法定記載事項以外の任意的記載事項についても、後の紛争防止という観点から適切に記載することが重要です。特に支払いに関する事項は争いになりやすいため、第三者(管理者や収集運搬業者)を介して支払いが行われる場合には注意が必要です。
例えば、排出事業者が管理者や収集運搬業者に費用を支払ったにもかかわらず、それらの業者が経済的に行き詰まって処理業者に支払わない事態も起こりえます。このような場合に備えて、処理業者が「勝てる契約書」とするためには「排出事業者は、管理者または収集運搬業者に処理委託費用を支払った場合であっても、受託者が処理費用を受け取るまでは支払義務を免れない」などの条項を入れておくことが望ましいでしょう。
産業廃棄物処理委託契約書は単なる形式ではなく、排出事業者責任を明確にし、適正処理を確保するための重要な法的文書です。必要事項をすべて記載した上で、将来の紛争を防ぐ観点からも慎重に作成することをお勧めします。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
