INDUST2021年1月号に「『健全な水循環を保全するための条例』に定める規制対象事業の認定処分取消請求訴訟」が掲載されました
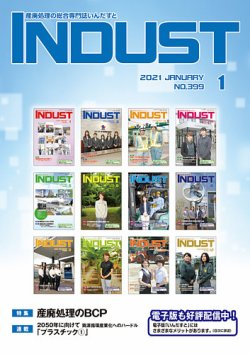
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2021年1月号に「『健全な水循環を保全するための条例』に定める規制対象事業の認定処分取消請求訴訟」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2065043/
本件は、岩石採取事業が条例によって制限された際に、岩石事業者から行政訴訟が提起されたものです。廃棄物処理業と条例も常に問題となるものであり、とくに環境条例によって事業活動が制限されたという状況は廃棄物処理業にも起こりうる状況であり、本件の判例の考え方は参考になるものと思われます。
事案の概要
Xは、平成21年3月頃、岩石採取計画の認可を受けて採石業を営んでいたA社より事業承継を受け、それ以降、本件規制の対象となった土地を含む一帯の土地において、従来より砂利採取、採石業等を営んできた会社です。本件土地が所在するY町は、平成25年6月に「健全な水循環を保全するための条例」(以下「本条例」)を制定しました。
本条例は、Y町長が水源保護地域または水源涵養保全地域に指定した地域において、規制対象事業に該当すると認定された事業を行うことを禁止しています。Xは、平成28年9月9日付で、処分庁に対して、本件各土地で砕石事業を行おうとしている旨届け出ました。本件土地は水源涵養保全地域内にあります。
処分庁は、本件事業は規制対象事業に該当すると認定するとの処分(本件処分)を行いました。その結果、Xは本件事業を行うことができなくなりました。Xは、平成28年11月25日付けで、山形県に対して岩石採取計画の認可の申請を行いましたが、山形県は、本条例に基づく規制対象事業に該当しない旨の認定結果通知書を申請書に添付していないことが書類の不備に当たるとして、認可を拒否するとの処分を行いました。これを受けてXは、平成29年2月20日、本件訴訟を提起しました。
争点
争点は多岐にわたりましたが、以下の二点についてご紹介します。
① 本条例が採石法に抵触して無効か。
② 処分行政庁に本件処分に当たって指導配慮義務違反があるか。
① 本条例が採石法に抵触して無効か
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決する必要があります。
採石法の目的は、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発展を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することにあります。一方、本条例は、Y町の健全な水循環の保全を図ることを目的としており、そのために地下水に影響があると認められる行為の一つとして岩石採取を規制しています。
両者は岩石の採取を規制するという点で共通するものの、採石法は採石業に伴う災害を防止することを目的とするのに対し、本条例は健全な水循環を保全するために岩石採取の規制を定めているのであり、採石法と本条例の目的は異なるものであると認められます。
本条例は一定の範囲で岩石の採取を規制するものではありますが、Y町内における岩石の採取を全面的に禁止するものではなく、飽くまで水源保護地域等内での土石又は砂利を採取する事業であって、水源涵養機能を著しく阻害するおそれや地下水脈を損傷するおそれがある事業等の実施を禁止するにとどまるため、採石法の目的である岩石の採取に伴う災害を防止し、適正な採石業の発展を図るという採石法の効果を阻害するものではないとされました。
したがって、本条例は採石法に矛盾抵触しているとは認められず、無効であるとはいえないと判断されました。
② 処分行政庁に本件処分に当たって指導配慮義務違反があるか
本条例は、届出に係る事業が規制対象事業に該当すると認定された場合、事業者は当該事業を実施することができなくなるという重大な制限を受けることを考慮すると、事前協議は本条例において重要な位置を占める手続であるといえます。そのため、処分行政庁が原告に対して本件事業が規制対象事業に該当すると認定するとの処分をするに当たって、処分行政庁ないし被告は、原告と十分に協議を尽くし、原告の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があったというべきであるとされました。しかし、原告が平成28年9月9日付けで本件届出をした際には、以下の事情があったため、被告ないし処分行政庁に指導配慮義務違反があったとは認められないと判断されました。
原告は、本件届出に、規制対象事業に該当しない事業となり得る「地表から地下2メートルの深さを超えない範囲で土石を採取する事業」におよそ該当し得ない事業を実施する予定である旨の計画書を添付した。
原告は、Y町の住民を対象とした説明会でも、住民らに歩み寄る姿勢は見せていない。
原告は、処分行政庁からの資料提供の依頼についても、これを拒否した。
原告は、被告からの協議の要請に対しても、本件届出から60日以内の日では原告代表者の都合がつかないとして上記期間を超えた日を指定するなどした。
これらの経緯に照らすと、被告ないし処分行政庁が、本件届出から本件処分までの間に、原告の地位に配慮した措置を執ったとしても、その措置が何らかの形で本件処分の内容に影響を及ぼし得たと認めることはできないというべきであるとされました。
考察
(1) 条例と法令の関係について(徳島市公安条例事件「目的・効果基準」)
本件条例は、Xが本件土地において採石業を行っていることを知りながら、Xの採石業を制限する目的で制定されたともいうべき条例であり(「狙い撃ち条例」)、このような条例が採石法との関係で許されるかが問題となりました。
条例と法律の関係については、条例は法律にとって下位の法令にあたり、「法律の範囲内」で、「法律に違反しない限り」においてのみ制定が許されているものです(憲法第94条、地方自治法第14条第1項)。当該条例が法律に違反しないか否かを判断するにあたっては、「目的・効果基準」が用いられ、徳島市公安条例事件(最高裁昭和50年9月10日)で示されました。
本件もこの「目的・効果基準」の枠組みにしたがって判断し、本条例は「採石法の目的である岩石の採取に伴う災害を防止し、適正な採石業の発展を図るという採石法の効果を阻害するものではない」として、法律に違反しないとしました。
(2) Y町の指導義務違反について
本件「規制対象事業」に認定されると、Xは本件事業を行うことができないという職業選択の自由に対する重大な制限を受けることになります。そのため、本件認定手続きは本条例において重要な地位を占める手続きであるということができます。
Y町がXが行おうとする事業を認識していた場合には、「Y町長は、本件届出より前に、Y町の水循環の保全の必要性と原告の本件事業実施の必要性とを調和させるためにどのような措置を執るべきかを検討する機会を与えられていた」というべきであり、「処分行政庁が原告に対して本件事業が規制対象事業に該当すると認定するとの処分をするに当たって、処分行政庁ないし被告は、原告と十分に協議を尽くし、原告の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があった」としています。
この判断は、紀伊長島町水道水源保護条例事件判決(最高裁平成16年12月24日)にしたがったものであり、廃棄物処理業事業が条例に抵触するとされた際にも参考となるものです。
しかし本件においては、Xが協力し指導に従う意思を見せておらず、Y町がXの「地位に配慮した措置を執ったとしても、その措置が何らかの形で本件処分の内容に影響を及ぼし得たと認めることはできない」として、Y町に具体的指導義務違反はないとしました。
私としては、廃棄物処理業においても同様の事案が想定されるため、本判例は重要な先例になると考えます。特に、環境保全等を目的とする条例と廃棄物処理法との関係で紛争が発生した場合、両者の目的の違いと効果の阻害の有無が判断の重要な基準となることを念頭に置いておく必要があります。また、行政には事業者の地位に配慮する義務があることも押さえておくべきでしょう。
本稿ではより詳しく解説していきます。
ぜひご覧ください。
