INDUST2021年10月号に「アスベストと企業の責任」が掲載されました
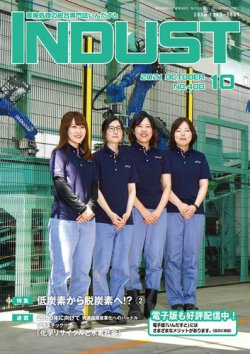
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2021年10月号に「アスベストと企業の責任」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2169316/
前回は、アスベストに関する法規制がどのようになされてきたか、また、令和3年5月17日建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決(以下、「令和3年最高裁判決」)をご紹介しました。本稿では、会社が自社の従業員に対してアスベスト被害を与えてしまった場合にどう考えるべきか、ということに対して焦点を当てていきます。
会社が従業員に対してアスベスト被害を与えてしまった場合の法的責任
①刑事責任(刑事罰)
解体などを請け負う会社は、解体を行うにあたっては解体の対象となる建築物に対してアスベストが含まれているか否かについて解体前に調査を行い、アスベストが含まれていることが判明した場合には解体作業計画を作成し、法に定められた作業基準にしたがって解体作業を実施しなければなりません。それにもかかわらず、事前調査を行わず、あるいは、作業基準を守らずに解体作業を行った場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」刑の対象となります。
②民事責任(損害賠償責任)
アスベストは、吸引することにより中皮腫、肺がん等の重篤な健康被害をもたらすものであることから、解体前の事前調査を行わず、あるいは、作業基準を守らずに解体作業を行った結果として、従業員に中皮腫等の健康被害が発生してしまった場合、会社は従業員に対して安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任、または不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
ア債務不履行責任
判例上、会社は、従業員との雇用契約に内在する責任として従業員が安全に業務に従事する環境を整える責任があるとされています。解体前の事前調査を怠り、または、作業基準に違反した解体を行うことは、従業員に対する安全配慮義務に違反した行為であり、これによって従業員の生命、身体の安全を害した場合には、安全配慮義務に違反したことによる損害賠償責任を負うと解されます。一方、会社が、解体前の事前調査義務、あるいは作業基準に違反することにより従業員の生命、身体を害した場合には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」として、従業員に対する損害賠償義務を負うことになります。
イ 不法行為責任
廃棄物処理業に即して考える場合、廃棄物処理の過程で適切な梱包を行わずに石綿含有廃棄物を収集運搬したなど、廃棄物処理基準に違反した処理が行われた結果、従業員に対して中皮腫等の健康上の被害が発生した場合にも、会社は従業員に対して安全配慮義務違反または不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。なお、不法行為に基づく損害賠償責任の時効期間は3年、除斥期間は20年とされます(民法724条)。除斥期間とは、一定期間権利を行使しないことにより、その権利を失うことになる期間のことをいいます。しかしアスベスト吸引によって健康被害が生じるまでの期間(潜伏期間)は10年から50年と長いものであり、多くの場合において健康上の症状が発現した場合には、すでに除斥期間は経過していることになります。そのため最高裁は、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる」としています(最判平成16年4月27日、筑豊じん肺訴訟)。
判例
会社の業務を行う中でアスベストを被ばくした者から会社に対して損害賠償請求を行った事例をご紹介いたします。
Aは、平成2年〜平成17年の間、ビルメンテナンスを行うB社と雇用契約を締結したうえで、B社が管理するC市立総合体育館の現場管理責任者として従事していました。Aが勤務している体育館には、天井裏、壁または天井には、吹付け石綿または石綿含有率が12%ないし14.5%の吹付けロックウールがそれぞれ施され、一部の吹付けロックウールは、劣化のため剥落し、粉状になって床に落ちていました。体育館ではそれらほこりが舞い上がっていたことが認定されています。このような環境下において、Aは体育館内の電気機械設備の管理や点検等に当たったり、自ら岩綿化粧板の取替作業を行うこともありました。これらを総合すると、Aは、石綿粉じんが飛散する場所で、石綿粉じんばく露の危険性を有する作業に従事していたということができるとされています。このような事実関係のもとで、B社のAに対する安全配慮義務違反が認められるかどうかが争われました。
前提となる事実
平成14年、国会における国務大臣の答弁において、「ビルメンテナンス作業や電気設備工事作業において、…事業者は、特定化学物質等障害予防規則の規定により、石綿を浸潤な状態にするとともに、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護具を使用させること、労働者が石綿を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること等が義務付けられて」いると発言しています。
また、公益社団法人ビルメンテナンス協会は、平成18年頃、各都道府県協会に対する通知において、ビルメンテナンス会社の従業員は、石綿が使用されている機械室等で作業に当たることによって、石綿にばく露し、健康被害を受ける可能性があること、及び、ビルメンテナンス会社は、その従業員の石綿ばく露による健康被害を防止するための措置を講じる義務や、従業員が就業する建築物に吹付けられた石綿等が損傷、劣化等により石綿粉じんにばく露する可能性があるときは、ビルメンテナンス業務の発注元に対して、石綿の除去等の措置を講じるよう求めなければならない義務があること等が記載されています。
安全配慮義務違反の有無及び具体的内容
本件体育館は、全国において石綿吹付け作業がピークを迎えていた昭和48年に竣工した総合体育館であり、石綿含有吹付け材が使用されている可能性は高かったといえます。また、昭和62年頃には、学校施設等における石綿の存在が大きな社会問題となっており、同年頃には、ビルや学校施設で吹付け石綿が使用されている可能性が高いと指摘されていたこと等が認められます。
そのため「石綿粉じんの発生及び飛散の防止並びに粉じん吸入の防止についてその時期に応じて必要な措置を講じ、従業員の生命・健康に重大な障害が生じることを防止するために、①被告市に対し、本件体育館の石綿の使用状況についての調査・確認すべき義務を負っており、これを前提とした②防じんマスクの着用確保義務及び③防じん教育義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務をいずれも怠ったといえるから、その余の義務違反の有無について判断するまでもなく、B社は、上記安全配慮義務に違反するものというべきである。」とされました。
前回ご紹介したとおり、建築物にアスベストが利用されたピークは1974年から1988年の間にあることを考えると、現在利用されている建築物にはアスベストはまだまだ残されており、日常的ビル管理及び改修、解体の場面でアスベストに被爆する可能性があります。そして、これらの建物の解体のピークは令和10年頃になるであろうとされています。
解体に携わる者だけでなく、解体廃棄物を扱う者もアスベストに被爆する可能性があること、これらの業務の過程において従業員がアスベストに被爆した場合、企業は、10年から50年後に安全配慮義務違反に基づく責任を追及される可能性があることを十分留意する必要があります。
本稿ではより詳しく解説していきます。
ぜひご覧ください。
