INDUST2024年10月号に「プラスチック資源循環促進法その後」が掲載されました
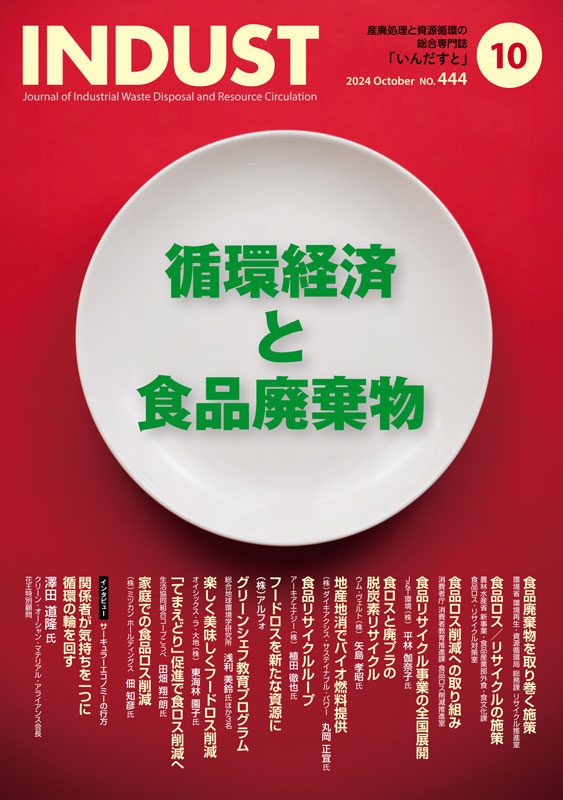
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年10月号に「プラスチック資源循環促進法その後」が掲載されました。zensanpairen.or.jp/books/indust/16840/
今回は、プラ新法施行後、どのような取組みが行われているかなどについてご紹介したいと思います。
プラ新法は、プラスチックの利用を最小限にし、製品はなるべく長く使い、廃棄時にはリサイクルを踏まえた戦略的分別を徹底することで、プラスチック資源の循環的利用を推進する法律です。この法律は製造業者、国民、排出事業者、処理業者、自治体など全ての関係者に対して、製造、使用、排出、再資源化の各段階でそれぞれの役割を果たすよう求めています。
この法律の背景には、プラスチックごみの海洋流出による環境汚染や、焼却時のCO2排出による地球温暖化の問題があります。また、プラスチックが自然界で分解しにくいという特性から、海洋生物への影響や食物連鎖を通じた人体への影響も懸念されています。そのため、プラスチック製品の使用・廃棄削減と並行して、自然界で分解するバイオプラスチックの開発・導入も推進されています。政府は2030年までにバイオプラスチックの導入量を年間約200万トンにする目標を掲げており、国内プラスチック生産量(2018年約1000万トン)の約5分の1をバイオプラスチックに置き換える計画です。
プラ新法施行以来、国民や製造業者の間でプラスチック削減への意識が高まっているように感じます。こうした意識変化がプラスチック使用の削減やバイオプラスチックの導入を促進し、目標達成あるいはその前倒しにつながることを期待しています。
プラ新法が設けている具体的制度とその進展状況は以下の通りです。
第一に、プラスチック使用製品設計指針の策定と適合製品の認定制度があります。長く使用でき、リサイクルしやすい製品設計を促進し、認定製品は国の機関や自治体が率先して調達することになっています。例えば花王は、ハンドソープの詰め替え用パックを単一素材化することで、同一製品から同一製品を生み出す水平リサイクルを可能にしました。
第二に、市町村による分別収集と再商品化の推進があります。プラ新法施行前は、容器包装プラスチックと製品プラスチックは別々に扱われていましたが、一括して扱えばより資源化しやすく、収集運搬から排出されるCO2の削減にもなります。市町村が再商品化計画の認定を受けることで、一括回収・再資源化が可能になりました。2022年9月に第1号認定を受けた仙台市を皮切りに、2024年5月時点で認定自治体は16に達しています。
第三に、製造業者による自主回収・再資源化の促進があります。製造業者が自社製品について自主回収・再資源化計画を作成し認定を受ければ、廃棄物処理法の許可なしに収集運搬や中間処理が可能になります。2024年7月時点で4件の認定があり、例えば積水化成品工業は6県1府で使用済み発泡スチロールを回収・リサイクルし、自社の原料として利用しています。また、緑川化成工業はコロナ禍で使用された飛沫防止パネルのリサイクルを行っています。
第四に、排出事業者による再資源化の促進があります。排出事業者も再資源化計画の認定を受ければ、複数社でチームを組んで廃棄物の収集・中間処理が可能になります。2024年7月時点で5件の認定があり、例えば浪速運送はアパレル業界の複数の排出事業者からプラスチックフィルムを回収・リサイクルしてペレットを製造しています。
プラ新法は罰則が少ないソフトな法律ではありますが、各主体の取り組みを促進する仕組みとして着実に機能しています。今後もプラスチック資源循環の推進に向けた様々な取り組みが広がることを期待しています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
