INDUST2024年12月号に「第二次キンキクリーンセンター事件高裁判決」が掲載されました
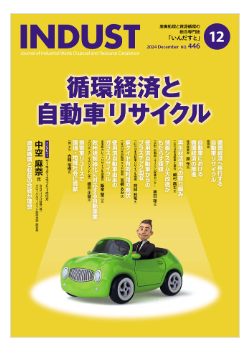
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年12月号に「第二次キンキクリーンセンター事件高裁判決」が掲載されました。
zensanpairen.or.jp/books/indust/20761/
今回は行政間で廃棄物処理費用の負担を巡って争われた「キンキクリーンセンター事件」の第二次訴訟高裁判決について解説します。本件は、先の第一次訴訟および第二次訴訟第一審とは異なる結論が示された注目すべき事例です。
福井県敦賀市にあるキンキクリーンセンターという最終処分場では、許可容量9万㎥に対し、その10倍以上となる119万㎥もの廃棄物が不法に搬入されていました。さらに近隣の川から基準値以上の汚染水の流入が認められたため、搬入量全量について不法投棄との認定がなされ、許可取消処分が行われました。
搬入された廃棄物は産業廃棄物が7割、一般廃棄物が3割と認定され、福井県がいったん全量の処理費用を負担した後、一般廃棄物の処理費用相当額として19億9948万円を敦賀市に請求しました。敦賀市はこれを支払った後、不法投棄された一般廃棄物の排出団体約60団体に対して費用負担を請求しました。多くの自治体は支払いに応じましたが、一部の自治体が拒否したため、敦賀市が訴訟を提起することとなったのです。
敦賀市が津山圏域東部衛生施設組合に対して提起した訴訟を第一次訴訟、南那須組合、東金市組合、高座組合、穂高組合、下諏町に対して提起した訴訟を第二次訴訟と呼びます。敦賀市の請求の法的根拠は、「事務管理」に基づく費用償還請求でした。
事務管理とは民法上の制度で、「他人の事務」を義務なく行うことをいいます。例えば、頼まれずに病人を病院に連れて行くなどの行為がこれに当たります。事務管理が成立すると、管理者は本人に対して支出した費用の償還を請求できます。ただし、事務管理の成立には「他人のために」行うこと、「他人の意思に反しないこと、あるいは本人のために不利であることが明らかでないこと」が必要です。
本件で問題となったのは、敦賀市が実施した廃棄物の撤去・無害化等の対策工事が、排出自治体のための行為(事務管理)に当たるかという点でした。事務管理に基づく請求では、被事務管理者に帰責性は要求されません。これは各排出自治体の帰責性を立証することが困難だったため、敦賀市が選択した法的構成と考えられます。
第一次訴訟の第一審(福井地裁平成29年9月27日判決)では、自治体は「一般廃棄物の処理についての統括的な責任」を負っており、廃棄物の不適正処理によって生活環境保全上の支障が生じた場合には「支障除去等の包括的措置義務」を負うとして、敦賀市の事務管理に基づく請求を認めました。第二次訴訟の第一審も同様の理由で敦賀市の請求を認容しました。
しかし、第二次訴訟の控訴審(名古屋高裁令和4年12月7日判決)は、これまでの判断を覆し、事務管理に基づく費用償還請求を否定しました。高裁は、自治体が一般廃棄物について統括的責任を負うことは認めつつも、「それだけでは一般的・抽象的責任をいうものにすぎず」、排出自治体が区域外での不適切処分に対して支障除去措置を講ずる義務を直ちに負うわけではないと判断したのです。
高裁判決はさらに、「地方公共団体の権限が及ぶ地理的範囲は、原則としてその区域内に限られる」として、区域外に権限を及ぼすには特別の定めが必要であるが、そのような規定はないと指摘しました。そして、「措置を命ずる権限がないにもかかわらず、また、自ら履行する術がないにもかかわらず、必要な措置を講ずる義務を負わせることは、排出自治体に不可能を強いるものである」として、区域外での支障除去義務を否定したのです。
この高裁判決は「法は不可能を強いるものではない」という法の基本原則に立ち返ったものと評価できます。事務管理構成は、排出自治体に廃掃法上の帰責性が認められなくても、自治体の一般廃棄物に対する統括的責任から何とか責任を負わせられないかという苦肉の策だったと思われますが、廃掃法上の帰責性がないにもかかわらず責任を認めるところに法としての矛盾がありました。
自治体が一般廃棄物の処理について負っている統括的責任の意味が改めて問われるところですが、高裁判決が示唆するように、この問題は立法的な対応が必要な領域だと考えられます。行政区域を越えた廃棄物処理の責任分担については、より明確な法的枠組みの構築が求められているのです。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
