INDUST2017年6月号に「廃棄物処理法改正法案★大分析 ~『意見具申』にみる改正法の基本的視点~」が掲載されました
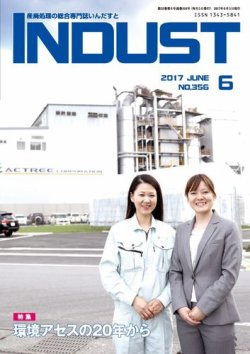
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2017年6月号に「廃棄物処理法改正法案★大分析 ~「意見具申」にみる改正法の基本的視点~」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1506597/
廃棄物処理法は5年ごとに見直されており、2010年の改正法施行から5年が経過したことを受け、2016年5月から中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会で8回にわたる議論が行われました。2017年2月14日には「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が環境大臣に提出され、これを基に同年3月10日に改正法案が閣議決定されました。改正法案のみを見るだけでは、廃棄物処理制度についてどのような議論がなされ、どのような方向性が検討されたのかを把握することは難しいため、意見具申に示された視点と法案に実際に取り入れられた内容を分析することが重要です。
「意見具申」におけるこれからの廃棄物処理制度の基本的視点
「意見具申」においては,「適正な循環的利用の徹底を図ったうえでなお循環的利用が行われないものについては適正な処分が確保されなければならない」として、まず「排出抑制」が重要であることを述べ、次に排出抑制を行った結果、なお廃棄物として処理が必要なものについては「適正な処分」の確保が必要としています。そして、その際、一層の電子化の推進と、今後の少子高齢化・人口減少社会が進むこと、地球温暖化対策が必要であることに留意する必要があるとしています。そのため、廃棄物処理制度について検討するにあたっては、以下の視点にたって検討を行うとしています。
⑴「適正処理のさらなる推進」
①排出事業者責任の更なる徹底
廃棄物処理法が排出事業者責任の原則を採っているにも関わらず、同原則が排出事業者に適切に認識されていないということは多くの場面において指摘されることであり、この原則の更なる徹底を推進するとされています。
②処理業者による適正処理の確保に向けた仕組みづくり
これは「適正な処理を行う業者が不適正な処理を安価で行う業者よりも優位に立つことができる仕組みづくりを行う」ことであるとされています。また、そのために「適正に処理する業者が円滑に事業活動を行えるよう不適正処理を招くことにならないよう配慮しつつ、(廃棄物処理制度を)合理的な制度とする必要がある」とされています。
③現場での機動的な対処をを重視した仕組みづくり
まず1つ目に「規制の現場」での行政の迅速かつ適正な対処を可能とする仕組づくりという視点が必要とされています。これには食品廃棄物の不適正転売事件(ダイコー事件)が大きな影響を及ぼしているといえます。2つ目に産業廃棄物処理の広域化に鑑み、法制度の統一的運用という視点が必要とされています。これは「事業の円滑化のための廃棄物処理制度の合理化」という視点と並び、事業者の立場に立った改正の視点として大きく注目されるところです。
⑵「健全な資源循環の推進」
①排出抑制・適正な循環的利用の推進
できる限り排出を抑制し、廃棄物となったものについては、再使用、再生利用、熱回収の順に循環的利用を行うことが重要とされています。
②優良な循環産業の更なる育成および各種手続等の合理化
ここでも優良事業者の育成という視点と廃棄物処理法に関する各種手続の合理化の視点が示されています。
「意見具申」にみる廃棄物処理制度見直しの主な論点
⑴産業廃棄物の処理状況の透明性向上
現状と課題
ダイコー事件の発覚を受け、食品廃棄物については再発防止策が執られています。
見直しの方向性
再発防止策については食品廃棄物のみならず産業廃棄物についても順次取り組みを広げていくこと、引き続き都道府県等による事業者に対する監視体制の強化を通じた透明性と信頼性の強化を進めていくべきとしています。とくに中間処理業者が再生を行う場合、排出事業者が再生利用の状況を確認することが不適正処理の未然防止の観点から極めて重要です。
改正法
見直しの方向性については今回の改正法案には盛り込まれませんでした。今後の検討課題となります。
⑵マニフェストの活用
ア マニフェストの虚偽記載等の防止
現状と課題
ダイコー事件による電子マニフェストを利用した虚偽報告事例等、マニフェスト虚偽記載等が行われていると指摘されています。
見直しの方向性
①虚偽登録・報告内容の疑いの検知等、電子マニフェストシステムの改善
②マニフェスト虚偽記載等を行った場合には措置命令(第19条の5)の対象となることの周知
③罰則の強化
改正法
改正法案において,マニフェスト虚偽記載等、マニフェストの規制義務違反について罰則が強化され、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました(現行法第29条第3号~12号:「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」)。
イ 電子マニフェストの普及拡大
現状と課題
電子マニフェストは、処理状況の透明性を向上させることで、不適正処理の未然防止や原因究明の迅速化等を図ることや、事務の効率化・合理化を期待できます。排出事業者,事業者,都道府県,国等の関係各者にとって大きな効力を発揮するものの、平成28年10月末現在の電子マニフェスト普及率は45%であるとしています。
見直しの方向性
①一定規模以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者について電子マニフェストの使用を義務付ける。
②電子マニフェスト加入促進のための各種取組の推進。
③マニフェスト虚偽記載等の防止に資するシステムの強化。
④分かりやすい講習会の開催等の普及啓発や電子マニフェスト導入にあたっての経済的負担の軽減等の検討。
改正法案
一定規模以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者について電子マニフェストの使用が義務付けられました(改正法案第12条の5第1項)。「一定規模以上」等具体的内容については環境省令で定められることとなります。その他の見直し事項については今後の検討課題となります。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
引き続き次回も改正法案についてご紹介させていただきます。
