INDUST2018年1月号に「住民同意の問題点と見直しの方向性」が掲載されました。
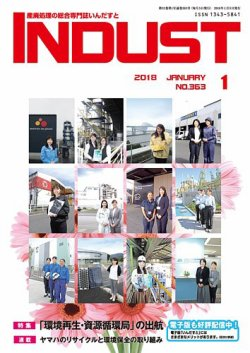
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年1月号に「住民同意の問題点と見直しの方向性」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1613348/
平成29年改正法制定に先立ち、環境中央審議会より「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が行われましたが、同意見具申における廃棄物処理制度の見直しの必要があるものとして地方自治体の運用について下記のような指摘が行われました。
「実質的な住民同意についても、その実態を把握した上で、廃棄物の円滑で適正な処理を阻害するおそれがあることを通知等により周知するなど、必要な措置を講じる必要がある。」
今回は、この「住民同意」について検討してみたいと思います。
住民同意とは?
住民同意とは、廃棄物処理施設の設置許可申請に先立ち、施設設置について住民の同意を得ることを指します。しかし、これは廃掃法上の要件ではありません。廃棄物処理施設は国のインフラとして必要不可欠ですが、多くの住民にとって「近所にはほしくない」施設です。そのため、住民同意を法的要件とすると施設設置が事実上不可能になるおそれがあります。代わりに法律では、監督行政庁が施設の安全性や適切性を判断するための詳細な規定を設けています。
なぜ住民同意が要請されるのか
①将来の紛争の防止
計画されている処理施設の概要を住民に説明し,周知を図ることによって,処理施設に対する住民の理解を深め,また,事業者に対する信頼を形成することができれば将来の紛争の防止をすることが期待できます。
②環境保全協定の締結
どのような施設ができるのかを住民説明会等で予め説明することによって、現在予定されている施設(操業方法)だと同意できないが、このように改善してくれれば同意できる、という場合があるかもしれません。それを基に住民と事業者との間で環境保全協定を締結することができれば、相互理解を促進することができます。また環境保全協定は住民の要望を吸い上げる形で事業者と自治体との間で締結されることもあります。
もっとも環境保全協定は、法令の基準を超え住民、あるいは自治体との間で締結するものであり、民法上の契約としての性質を有するものと考えられます。そのためいったん環境保全協定を締結すると,事業者はこの「契約」の内容に拘束されるため、事業者は慎重にそのリスクを検討するべきであるといえます。
平成22年「廃棄物処理法の見直しの方向性(意見具申)」(平成22年1月25日付中央環境審議会)において示された住民同意の問題性
①地域のコミュニティーの破壊
特に地方では地域のつながりが密接で、「賛成」の声をあげると地域の中で孤立してしまう可能性を住民が懸念し、「賛成」といえない状況があります。これは地域のコミュニティーの破壊をおそれた結果、住民同意が得られない場合です。これは事業者の側では解決することができない問題です。
また処理施設の設置によって地域に利益がもたらされる場合(たとえば,一定の雇用の確保,有益な施設の設置など)、反対派と賛成派で意見が分かれ,地域のコミュニティーが破壊されてしまうおそれがあります。
②処理施設設置手続きの長期化
住民同意が得られない場合においても、行政が「住民同意が得られない限り設置許可申請を受けられない」という態度を維持する場合には、結局事業者の側で設置を諦める場合もあります。
住民同意の法的根拠
法令上の義務はない(法的義務ではない)にもかかわらず、行政が事業者に要請することを「行政指導」といいます。行政指導とは,「行政が一定の目的を達成するために事業者に協力を求める行為」ということになります(行政手続法第2条第6号)。廃棄物処理施設の設置にあたり住民の同意を得ることを要請することはこの「行政指導」に当たります。この「住民同意を要する」とすることが「指導要綱」に規定されていることがありますが、「指導要綱」とは行政指導を文章化したものであり、行政指導であることに変わりはありません。
住民同意を得ることは不可能であると事業者が判断した場合、事業者はこれ以上住民同意を要するとする行政指導には従えないことの意思を表明して設置許可申請を行うことを検討することになります。その場合、行政との丁寧な打合せと説明が必要となることと思われますが、場合によっては弁護士等の専門家とともに行政に説明を行うなどの方法も考えられます。
平成22年及び平成29年意見具申における見直しの方向性
「廃棄物処理への不信感を解消し信頼感を醸成するためには,廃棄物処理によるリスクが正しく評価されるよう,施設の維持管理情報等を透明化する仕組みを設けることなどにより,廃棄物処理に関するリスクコミュニケーションを図っていくべきである」(平成22年意見具申)。
住民同意について「廃棄物の円滑で適正な処理を阻害するおそれがあることを通知等により周知するなど,必要な措置を講じる必要がある。」(平成29年意見具申)。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
