INDUST2018年7月号に「欠格要件制度の現状と対策」が掲載されました。
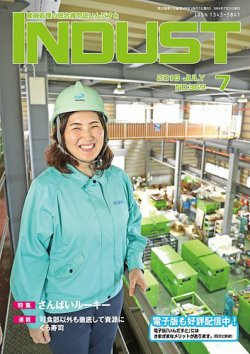
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2018年7月号に「欠格要件制度の現状と対策」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/1693862/
今回は、累次の改正により分かりにくくなった欠格要件制度の現状を確認するとともに、欠格要件制度の課題と今後の方向性、欠格要件制度から企業を守る対策を検討したいと思います。
欠格要件とは
欠格要件制度とは、法が定める一定の要件(事由)に該当した場合には廃棄物処理業の許可を与えないとするものです(法第7条第5項第4号、第14条第5項第2号)。また、欠格要件に該当した場合には、許可を得ていた場合であっても許可が取り消されます(法第14条の3の2)。この趣旨は、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を欠格者として類型化し、これらの者に許可を与えず、又は許可を取り消すことによって廃棄物処理業から排除することにあります。
欠格要件制度の現状と課題
⑴欠格要件該当による許可取消のうち、議論がある例
①会社の株式を有する者が成年被後見人に該当したことにより会社が許可取消の対象となる事例
会社の創業者Aが会社の株式の60%、Aの妻Bが株式の10%を有しており、息子Cが取締役社長をつとめている会社Xにおいて、Bが高齢のため認知症の症状が著しくなってきたので、成年後見人選任の申立てを行い成年被後見人の宣告を受けた。X社が許可更新の申請をしたところ成年被後見人Bが「みなし役員」に該当し、欠格要件に該当するとして許可取消処分を受けた。
この場合、Aの妻BはX社の株式の10%を保有していることから「みなし役員」とされ、成年被後見人であることは欠格要件に該当することからX社の許可が取り消されることになります(法第14条の3の2第1項第4号)。X社の株式10%を保有していることが「みなし役員」とされる根拠は、産業廃棄物処理業の許可の申請にあたって当該会社の発行済み株式総数の5%以上を保有する株主について届け出ることになっていることから(規則第9条の2第9号、同第10条の4第1項第9号)、当該会社の発行済株式総数の5%以上を保有する株主は、取締役ではなくても株主として会社の経営に対する支配力が大きいと考えられ、「役員とみなされる」ことによります。
② 役員が暴行罪により罰金刑を受けたことにより会社が許可取消の対象となる事例
Y社の役員Cが業務終了後、友人と飲食店で歓談し店を出たところ、路上でDと肩が触れ合い口論となった。DがCの胸倉を掴んだため、CがDの首元を押したところ、Dが倒れ、歩道脇のガードレールに脇腹を打ちつけ、全治3週間の打撲傷を負った。Cは罰金20万円の有罪判決を受けたため、Y社は欠格要件に該当するとして許可取消処分を受けた。
この場合、役員Cの行為は暴行罪(刑法208条)にあたり、罰金以上の有罪判決を得れば欠格要件に該当し(法第14条第5項第2号イ)、許可取消の対象となります(法第14条の3の2第1項第1号)。
③ 役員が道路交通法違反により禁錮刑を受けた場合に会社が許可取消の対象となる事例
Z社の役員Eは休日にドライブ中、スピード違反により現行犯逮捕された。Eは警察から停止の指示を受けたにもかかわらず、逃走を図ったため公務執行妨害罪でも検挙された。Eは道路交通法違反(スピード違反)及び公務執行妨害罪で禁錮1ヵ月、執行猶予6ヶ月の有罪判決を受けた。
この場合、Eは道路交通法違反、公務執行妨害罪で禁錮以上の刑に処されていることから欠格要件に該当し(法第14条第5項第2号イ)、Z社は許可取消の対象となります。
⑵ 連鎖規定
法人の役員が欠格要件に該当した場合で、行為の悪質性が高い場合には欠格要件が連鎖されるとされ、役員を共通する関連会社が許可取消になってしまう場合があります。ただ、この欠格要件の連鎖は、平成22年改正以前は、役員を共通にする限り無限に連鎖することとなっていましたが、平成22年改正により、欠格要件が連鎖するのは、廃掃法の趣旨からみて行為の悪質性が重大な取消事由に該当する場合に限定されました。すなわち、重大な取消事由に該当する場合とは、行為が廃掃法第25条から第27条に該当する場合、及び暴力団が関与した場合等のことをいいます。
例えば、上記⑴の②と③の事例の場合、CとEの行為は行為の悪質性が重大とまではいえず、欠格要件が連鎖する場合にあたりません。Cが役員をつとめるY社、Eが役員をつとめるZ社は許可取消の対象となりますが、Y社、Z社の関連会社には連鎖は波及しません。
4 欠格要件制度の課題
欠格要件の連鎖については、平成22年改正により無限連鎖に一定の制限が行われたことにより、適正に業務を行っている限りそれほど恐れる必要はないと考えられます。
これに対して、上記3の例のように、「みなし役員」とみなされる者の範囲が不明確であるとか、業務と無関係の理由により当該役員が欠格要件に該当するのみならず、会社も欠格要件に該当されてしまうことなどは、検討の課題であるとされています。
とくに、業務に関与していなかった株式保有者が成年被後見人の宣告を受けたことによって、その者ののみならず会社をも欠格要件に該当するとして許可を取り消すとするのはいかにも硬直的だと思われます。この点、欠格要件に該当する場合の許可取消を裁量的取消から義務的取消にあらためたことによる問題でもあると思われます。
平成29年2月14日付「廃棄物処理制度の見直しについて(意見具申)」においても、欠格要件の上記の課題については引き続き検討を行うとしています。
5 欠格要件制度の対策
⑴ 株式の分散を防ぐ・株式を集約する
上記3①の事例のように、役員とはなっていなくても5%以上の株式を保有している者は「役員」とみなされてしまう可能性があります。親族で株式を保有している場合、株式に譲渡制限が付されていたとしても相続により株式が分散されていく可能性があります。
会社としては、まず株主を把握し、会社から普段目の届かない株主からは株式を買い取るなど、株式を会社から目の届く距離に集約しておく必要があります。
事業承継の際などは、遺言により後継者に株式を集中的に相続させるなど、株式の分散を防ぐことが大切です。
⑵ ホールディングス化
関連会社が複数存在する場合、あるいは分社等により関連会社が複数となる場合、それらの会社の株式を保有することだけを目的とするホールディングス会社を作ることも考えられます。役員が欠格者となった場合、その者が役員をつとめる会社が欠格要件に該当することは避けられませんが、ホールディングス会社を作ることによって欠格要件の連鎖を防ぐことが可能です。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
