INDUST2020年8月号に「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)令和2年3月30日(環循規発第2003301号)」が掲載されました
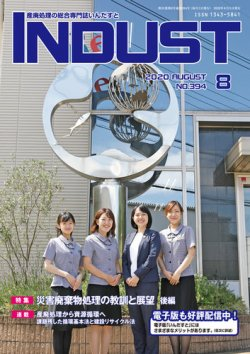
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2020年8月号に「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)令和2年3月30日(環循規発第2003301号)」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2010220/
本件通知は、平成30年3月30日に発出された産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」(環循規発第18033029号)について見直しを行ったものです。本稿では許可の性質と許可の施設に関する要件について気になった点をご紹介したいと思います。
産業廃棄物の業の許可は義務?!
廃棄物処理法は「当該業を行おうとする区域…を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定していますが、この「許可」は法的には「羈束裁量」であると解されています。「羈束裁量」とは、法令の要件を満たすかどうか判断することについてのみ裁量(判断権)が与えられており、法令の要件を満たす以上「許可しなければならない」(義務)という意味です。つまり、許可申請にあたり、業者の申請が法令の規定する要件を満たす限り都道府県知事は許可をしなければならない(義務)という意味です。本件通知は、「廃棄物処理法は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。」としています。
留意点①許可基準を満たすか否かについては裁量権がある
業者の許可申請が法令の要件を満たしているかどうかについては都道府県知事に判断権があります。許可申請が法令の要件を満たしているかどうかとは、すなわち、許可基準のことであり、許可基準とは、すなわち、①「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りること」(施設及び能力の基準)、及び②欠格要件に該当しないことです。
留意点②許可基準に関係のない指示は行政指導
指示された内容が許可基準にかからない場合、その指示の内容は「行政指導」であって、行政指導については「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」(行政手続法第32条第1項)と行政手続法に規定されているとおり、業者の側に「任意の協力」を行って指示に従うかどうかの判断が委ねられることになります。
施設を「継続的に使用する権限を有していること」
本件通知は、施設に関する基準を満たすかを判断するにあたっては「申請者が、当該申請に係る施設について、継続的に使用する権限を有していることを確認すること。」としています。
具体的には、たとえば、施設建物が存在している土地が賃貸借による場合、土地の賃貸借契約が存在し、賃借権が許可申請者に存在することが必要とされます。これらを土地の不動産登記及び賃貸借契約書の存在で確認することになります。
施設の基準に関して問題となった事例をいくつかご紹介します。いずれも許可を取得した後に問題となりました。
事例1 住民の反対運動と賃貸借契約の解除
許可申請者Aがある土地を地主Bから借りて土地上に中間処理施設を有していたところ、施設に反対の住民Cがその土地所有権を賃貸人から買い取り、土地所有権を買い取った後、賃貸借契約を解除しました。解除が有効であるとすると申請者の施設が存在する土地の賃貸借契約が存在しないことになり、施設は存在の根拠を失いますから、許可基準を満たさず、許可が取り消されることになります。
本件は、CからAに対して土地賃貸借契約解除を理由とする建物収去土地明渡請求訴訟が提起され、Aからは賃貸借契約解除無効の主張が行われ、土地賃貸借契約解除の有効性が問題となりました。土地所有権の取得が反対運動のための取得であり、反対運動のために土地賃貸借契約を解除したものであって、土地賃貸借契約の解除は土地所有権者としての正当な権利行使ではないとして、土地賃貸借契約の解除は認められませんでした。
申請者の自衛策として、施設の土地が他人所有である場合、できる限り土地所有権自体を確保しておく、賃貸人との関係を良好に保っておく、仮に土地を売却する場合には自分に売るように合意をしておくなどの対策をとっておく必要があると思われます。
事例2 事業承継
Dは父親Eと中間処理会社Fを創業し、共同経営していましたが、F社の株式は父親Eが100%保有していました。Eが急病で死亡し、遺言書どおりに会社に敷地となる土地の所有権は母親G(Eの妻)に、F社の株式は、Eの3人の子が3分の1ずつ保有することになりました。DはF社の代表取締役に就任しました。
ところが、経営方針を巡ってDと母親G、Dの兄弟であるH、Iは対立するようになり、母親Gは、Dが代表取締役を辞任しない限り土地の会社に対する賃貸借契約を解除すると通告してきました。そこで、やむなくDは、会社を守るためF社の代表取締役を辞任しました。
会社の中間処理施設の敷地の賃貸借契約が解除されれば会社は存在の根拠を失いますから許可の施設に関する基準を満たさなくなり、事例1と同様に許可取消となります。そこで、Dとしては、会社を守るためにやむなく代表取締役を退いたということになります。
本件は、Dが代表取締役を退いた後に、母親Gや兄弟H、Iを訴えることはできないかとご相談にみえましたが、どうすることもできませんでした。このようなことを防ぐために、会社の敷地や株式については、事業承継が発生する前に後継者に承継されるよう遺言書を作成しておくなどの対策を立てておく必要があります。
これらの事例から学べることは、廃棄物処理業において施設の基準を満たすためには、土地の権利関係を確実に保全することが非常に重要だということです。特に事例2のような家族経営の会社では、事業承継を見据えた計画を早期に立て、土地所有権や会社支配権についてのリスクを予防することが不可欠です。
施設の土地の賃貸借関係が不安定であれば、いかに優れた施設や運営体制を持っていても、許可の維持が危うくなります。できる限り土地所有権を自社で確保する、あるいは長期的な賃貸借契約を締結し、地主との関係を良好に保つといった対策が重要でしょう。また、事業継承においては、経営権と施設用地の所有権が分離しないような事前の対策が必要です。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
