INDUST2022年8月号に「プラスチック資源循環促進法下における排出事業者による排出の抑制及び再資源化等 その1」が掲載されました
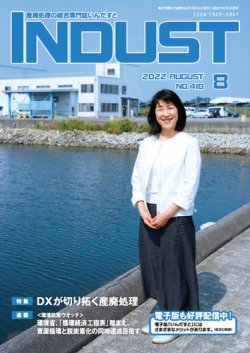
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2022年8月号に「プラスチック資源循環促進法下における排出事業者による排出の抑制及び再資源化等 その1」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2284917/
プラスチック資源循環促進法の下においては、製造業者等に対して自主回収及び再資源化義務が課されているほか、排出事業者に対しては排出抑制及び再資源化等の義務が課されています。これに関して、「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」が制定されるとともに、「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の 抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き」が制定されましたので今回と次回に分けてご紹介したいと思います。
プラ新法は、プラスチック使用製品の使用合理化、市町村による再商品化、製造事業者等による自主回収、排出事業者による排出抑制等を通じて、プラスチックの資源循環を目指す法律です。
排出抑制及び再資源化実施義務は、小規模事業者(従業員20人以下)を除くすべての排出事業者に課されています。特に前年度のプラスチック廃棄物排出量が250トン以上の多量排出事業者は、目標設定と計画的な取組実施が求められます。
プラ新法では、排出量は通常の廃棄物処理とは異なる考え方で算定されます。排出量には事業場外に出される廃棄物量だけでなく、自ら処理・再資源化する量も含まれます。また製品のライフサイクル全体を通した環境負荷に着目しています。排出量は法人単位で算定し、フランチャイズ事業や建設業には特別ルールがあります。フランチャイズでは一定条件下で加盟店の排出量が本部の排出量に含まれ、建設業では元請業者の排出量に含まれます。
プラ新法の下で排出事業者は、原材料使用の合理化や端材の有効活用、包装材の簡素化と代替素材への転換、そしてプラスチック製品の長期使用と過剰使用抑制などの排出抑制策を講じることが求められています。
また再資源化においては、リチウムイオン電池などの再資源化阻害物の混入防止対策を実施し、感染性廃棄物が付着しているケースなど再資源化が困難な場合には効率的な熱回収を行うか適切な業者に委託する必要があります。さらに、廃棄物の飛散・流出や悪臭発生など生活環境への悪影響を防止する措置も重要です。
次回は多量排出事業者の目標設定や情報公表など、より詳細な内容を解説する予定です。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
