INDUST 2024年11月号に「契約書作成の基本とポイント」が掲載されました
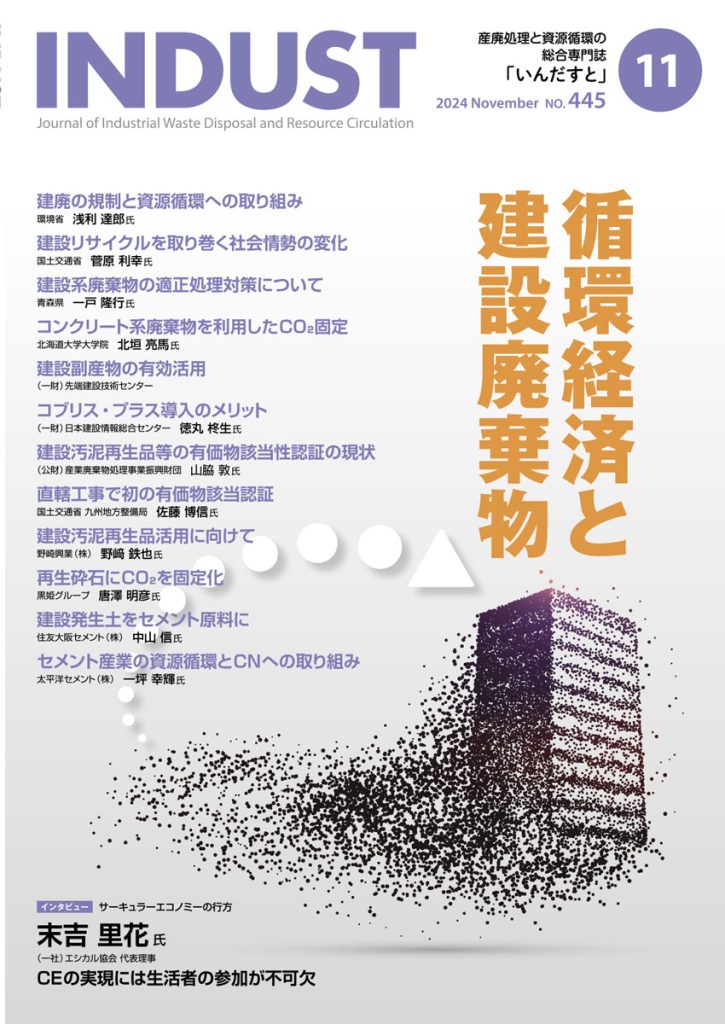
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年11月号に「契約書作成の基本とポイント」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2591345/
今回は廃棄物処理委託契約書作成の基本とポイントについて解説します。廃棄物処理委託契約書は廃棄物処理取引のスタートであり、取引上も法的責任の面でも極めて重要なものです。弊所での相談項目でも常に上位に位置する問題です。
1 産業廃棄物処理委託契約書は排出事業者の法的責任
⑴ 産業廃棄物処理委託契約書の作成義務
産業廃棄物処理委託契約書の作成は排出事業者の法的責任です。排出事業者は産業廃棄物の収集運搬または処分を委託する際、政令で定める委託基準に従わなければならず(廃棄物処理法第12条第6項)、その一つとして契約書作成が義務付けられています(同法施行令第6条第4号)。さらに契約書には法定の必要的記載事項をすべて記載しなければなりません。
もし契約書が作成されない場合や必要的記載事項が一つでも欠ける場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科される重い罰則が設けられています(法第26条第1号)。
⑵ 産業廃棄物委託契約書の作成の趣旨
ア 契約自由の原則
なぜこのように厳格な義務が課されているのでしょうか。一般的な民事契約では契約自由の原則により、契約を締結するかどうか、どのような内容の契約にするか、契約書を作成するかどうかは当事者の自由です。一般廃棄物についても契約書作成義務はありません。
イ 排出事業者責任の原則
しかし産業廃棄物処理については、排出事業者責任の原則に基づき、適正処理確保のために厳格な規制が設けられています。排出事業者責任とは「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(法第3条第1項)という責任であり、環境負荷の原因を作った者がその責任において適正に処理すべきという汚染者負担の原則に由来します。
具体的には、①自ら処理する場合は処理基準を遵守する義務、②他人に委託する場合は適正な業者に適正に委託する義務(委託基準遵守義務)、③委託後もマニフェスト管理等を通じて最終処分完了まで追跡・管理監督する義務があります。産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者がこの責任を全うするための第一歩なのです。
2 産業廃棄物処理委託契約書の必要的記載事項
⑴ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
数量に関しては、契約前は未定であるとして未記載の契約書が散見されますが、数量を記載しておかないと委託基準違反として、罰則の対象となる可能性があります。予定数量でよいので記載しておきましょう。
⑵ (収集運搬契約の場合)運搬の最終目的地
中間処理施設や最終処分場所など運搬先がどこかを記載しておきます。ある会社の中間処理施設に運搬する場合、当該会社の中間処理施設が複数ある場合もありますので、最終目的地の住所を記載しておくことが明確です。
⑶ (処分委託契約の場合)
① その処分または再生の場所の所在地、その処分または再生の方法およびその処分または再生に係る施設の処理能力
② 当該産業廃棄物が輸入廃棄物である場合はその旨
③ 中間処理を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法および最終処分に係る施設の処理能力
⑷ 委託契約の有効期間
自動更新条項が設けられることが多いですが、自動更新条項がない契約書の場合、いつの間にか有効期間が切れてしまっている場合があります。この場合において、産業廃棄物を運搬してしまうと契約書が不作成のまま運搬してしまったことになり委託基準違反(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科)となりますから留意が必要です。
⑸ 廃棄物処理委託費用
「どのくらいの料金になるか分からないので、請求書ベースでやっています」というような例をよく聞きます。しかしながら、予定で構わないので、一定の金額を記載するか、単価を記載しておくなど、委託費用の判断基準となる金額を記載しておく必要があります。
⑹ 受託者の事業範囲
収集運搬業なのか処分業(中間処理または最終処分)なのか、許可を受けている産業廃棄物の種類などを記載します。
⑺ 積替え保管に関する事項
受託者が積替え保管を行う場合には、当該積替えまたは保管を行う場所の所在地ならびに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類および当該場所に係る積替えのための保管上限を記載します。
⑻ 積替え保管の際の他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
積替え保管を行う場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替えまたは保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項を記載します。
⑼ 委託する廃棄物の適正処理のために必要な次に掲げる事項
① 当該産業廃棄物の性状および荷姿に関する事項
② 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
③ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
④ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
⑤ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
⑥ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
⑽ 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
契約期間中に、委託した廃棄物に係る情報に変更があった場合には、処理方法等に影響が生じる可能性があるため、これを処理業者に伝える必要がありますが、その伝達方法を契約書で記載しなければならないことになっています。「廃棄物に係る情報に変更があった場合には、甲は、速やかにメールによって乙に通知する。」等の記載を行っておけばよいでしょう。
⑾ 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
廃棄物の処理(収集運搬の場合は目的地まで運搬すること)が終了した場合には、受託者は委託者に対して処理が完了したことを報告しなければなりません。この報告をどのように行うかを契約書に記載しておく必要があります。通常はマニフェストをもって処理完了報告を行うなどと記載されています。
⑿ 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
廃棄物処理委託契約を解除したものの、依然として処理が完了していない廃棄物があった場合の取扱いを記載することとなっています。契約を解除したとはいえ、廃棄物が残っている限り排出事業者責任はなくなりませんが、処理業者側に解除に至った責任がある場合には、処理業者側において費用負担するなどの対応が求められるでしょう。
通常は、契約解除に至った責任の所在によって、残存している廃棄物について誰が費用負担をするか、誰が処理を行うかを決定します。
3 法定記載事項以外の記載
⑴ 任意的記載事項
また法定記載事項以外の任意的記載事項についても、後の紛争防止という観点から適切に記載することが重要です。特に支払いに関する事項は争いになりやすいため、第三者(管理者や収集運搬業者)を介して支払いが行われる場合には注意が必要です。
例えば、排出事業者が管理者や収集運搬業者に費用を支払ったにもかかわらず、それらの業者が経済的に行き詰まって処理業者に支払わない事態も起こりえます。このような場合に備えて、処理業者が「勝てる契約書」とするためには「排出事業者は、管理者または収集運搬業者に処理委託費用を支払った場合であっても、受託者が処理費用を受け取るまでは支払義務を免れない」などの条項を入れておくことが望ましいでしょう。
産業廃棄物処理委託契約書は単なる形式ではなく、排出事業者責任を明確にし、適正処理を確保するための重要な法的文書です。必要事項をすべて記載した上で、将来の紛争を防ぐ観点からも慎重に作成することをお勧めします。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
