INDUST2025年5月号に「『食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針』について」が掲載されました
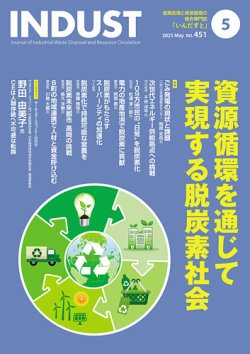
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2025年5月号に「『食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針』について」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/new/
令和7年3月14日、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」が告示されました。この基本方針は、令和6年8月2日に閣議決定された第五次循環型社会推進基本計画に則り、食品リサイクルの分野での具体化を図るものです。近年のカーボンニュートラルの達成、食糧安全保障の強化等を推進するため、本基本方針が改訂されました。
基本理念
食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階において、食品ロスの削減を含め食品廃棄物等の発生の抑制に優先的に取り組んだ上で、食品循環資源について再生利用、これが困難な場合には熱回収を行い、やむを得ず廃棄処分を行う食品廃棄物等は減量を推進し、環境への負荷の少ない循環型社会を構築していくことが必要とされています。
関係者の取組の方向
食品は、流通、消費、廃棄等の各段階において多くの者が関与しており、食品の循環経済を達成するためにはそれらの各段階で各関係者が排出抑制、再生利用等循環に対する役割を果たすことが期待されています。
食品関連事業者
食品関連事業者は、排出事業者としての責任を自覚し、自身が排出する食品廃棄物の排出(食品ロス)の抑制に努めるとともに、食品循環資源を利用して製造される肥料や飼料である特定肥料を用いて生産された農畜水産物等を利用することによって農林漁業者との安定的関係を構築し、地産地消や地域における食品資源循環の構築に努めることとされています。
さらに、自らの排出量、再生資源の再生利用等の状況、フードバンク等への食品寄付量等について、有価証券報告書や統合報告書等への記載、インターネットその他の方法を通じて情報提供するよう努めることとされています。
再生利用事業者及び農林漁業者
再生利用事業者は、食品関連事業者と農林漁業者等を結ぶ立場にあることから、食品循環資源の品質・安全性に関する情報を食品関連事業者に伝えるとともに、農林漁業者等の利用者のニーズに合った品質の特定肥飼料等の製造に努めるものとされています。
農林漁業者等は、再生利用への理解を深め、飼料自給率向上、環境保全型農業推進、地球温暖化防止等の観点から特定肥飼料等の積極的な利用に努めるものとされています。
消費者
消費者の排出する食品廃棄物は、令和4年において、食品廃棄物の量の約半分を占めています。外食産業からの食品ロス削減においては消費者による食べきりの実践が、また食品小売業者からの食品ロス削減には過度な品揃えを求めないなど、消費者の意識と行動の変革が不可欠とされています。消費者は自らの食生活が地域や地球環境に与える負荷を理解し、食品の購入・消費の各段階で食品廃棄物等の発生抑制に努めることが求められています。また、家庭からの食品廃棄物の発生抑制に取り組むことが重要です。
食品関連事業者以外の食品廃棄物等を発生させる者
食品関連事業者以外の者においても、食品関連事業者の取組に準じて、食品ロスの削減を含む食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めるものとされています。多様な主体の参加の下、社会全体で食品廃棄物等の削減等に取り組むことが重要です。
国
国は、情報提供と啓発活動、研究開発費用の支援等を行うことが求められています。例えば、特定肥飼料等の安定的な利用を図るため、国は食品循環資源由来の再生品活用を推進するための連携づくりを進め、エコフィード(食品循環資源を利用した飼料)に関する優良事例の紹介や講習会開催など、継続的施策を推進することが考えられます。
その他、食品循環資源の再生利用等に貢献する市町村の先進的取組事例を調査・公表するなど、地方自治体の取組を促進するための情報発信にも努めるものとされています。
地方公共団体
食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者等の連携を促進し、食品循環資源の再生利用等を推進するために必要な措置を講じるよう努めることが求められています。また、地域の関係者と協力して、食品ロスの削減を含む食品循環資源の再生利用等について、消費者等に対する普及啓発や教育活動の実施にも取り組むことが期待されています。
特に市町村は、管内の一般廃棄物処理に統括的な責任を持つ立場から、環境保全を前提としつつ、地域の実情に応じた食品循環資源の再生利用等を促進するための必要な措置を講じるよう努めることとされており、家庭から発生する食品廃棄物の発生抑制や食品循環資源の再生利用等についても、市町村が中心となってその促進に必要な措置を講じるよう努めることが求められています。
食品循環資源の再生利用についての優先順位は、①排出抑制(発生の抑制)→②再生利用(リサイクル)→③リサイクルできないものについては熱回収→④熱回収できないものについては「減量」したうえで最終処分する、という流れです。
①発生の抑制
食品廃棄物等の発生の抑制を最優先とされています。特に外食産業など散在する事業所から少量ずつ排出されることの多い食品廃棄物等について再生利用、熱回収又は減量を行うことは技術的・経済的・エネルギー的に制約が多いことからも、食品ロスの削減を始めとする食品廃棄物等の発生の抑制が有効かつ重要です。
②再生利用
食品廃棄物については、物の性質上リユースは存在せず、再生利用(リサイクル)が重要であり、様々な再生利用がされています。その際、食品循環資源は、腐敗しやすいという特性を有するものが多いという特性を踏まえ、カーボンニュートラルへの貢献への視点に留意しつつ生活環境保全の点に留意し関係法令を遵守することが重要です。
1飼料化
飼料化は、その物の成分や熱量(カロリー)を最も有効に活用できる手段であるのみならず、飼料自給率の向上にも寄与するとともに、輸入飼料に比べて安定した価格で流通するため畜産物の安定生産に資することから、優先的に選択すべきとされています。
2肥料化
飼料化が困難な場合には、可能な限り肥料化を行うことされています。もっとも、肥料化にあたっては、地域や市場における有機質肥料の需給状況等を十分に踏まえつつ、利用先の確保を前提とした上で実行していく必要があります。
3きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地への活用
食品循環資源をきのこ類の栽培のために使用される固形状の培地として活用することで、食品循環資源の有する成分の有効利用につながります。飼料化及び肥料化が困難な場合には、食品循環資源の性質、地域の菌床の需要等に応じて菌床への再生利用を行うとされています。
4飼料化、肥料化及び菌床への活用以外の再生利用(メタン化等)
飼料化、肥料化及び菌床への活用が困難な場合には、メタン化等の再生利用を行うこととされています。メタン化等への活用は化石燃料の使用とそれに伴う二酸化炭素の排出の削減を期待できることからカーボンニュートラルにも貢献するものです。
③熱回収
油分や塩分を多く含む食品循環資源は再生利用が困難な場合があり、そのような場合は熱回収による有効利用を検討すべきとされています。食品循環資源(バイオマス)の焼却熱利用は化石燃料使用量と二酸化炭素排出量の削減につながり、カーボンニュートラルに貢献します。
④減量
再生利用及び熱回収ができない食品廃棄物等については、腐敗しやすいという特性に鑑み、食品関連事業者が自ら脱水、乾燥、発酵又は炭化を実施することにより、廃棄処分される食品廃棄物等の重量を減少させ、その後の廃棄処分を容易にすることが重要とされています。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
