INDUST2025年6月号に「巨額損害賠償請求が認められたアスクルの倉庫火災に学ぶ企業のリスク管理」が掲載されました
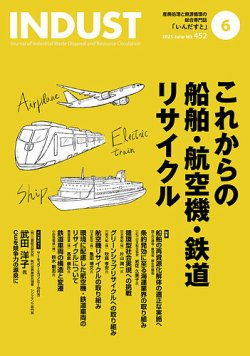
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2025年6月号に「巨額損害賠償請求が認められたアスクルの倉庫火災に学ぶ企業のリスク管理」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/new/
2017年2月16日に埼玉県三芳町に所在するアスクルの物流拠点で発生した火災は13日間にわたって燃え続け、約101億円の損失を出しました。
発生の原因は、アスクルと古紙に関する継続的売買契約を締結していた愛知県の古紙販売業者の過失であるとして、アスクルは、同社に対して101億円の損害賠償を求めて訴訟を東京地裁に提起しました。
一審判決が古紙販売業者に責任を認め、51億円の損害賠償を命じた理由はなんだったのか、また、高裁がこれを覆し、94億円の損害を命じた理由はなんだったのでしょうか。
これらから、我々として学ぶべきこと、対策は何なのか検証したいと思います。
1 事故概要
事故は、2017年(平成29年)2月16日午前9時ころ、埼玉県三芳町のアスクルの大規模倉庫において出火しました。
2 発生の原因
出火原因は、倉庫1階の北西部の段ボール置場であり、フォークリフトで段ボール回収作業を行っていた古紙回収業者の従業員の不適切な行為にあったとされました。回収業務を行っていた端材室には、当時、段ボール等の端材が1.5メートルから3メートルの高さに集積されていたとのことです。そのような状況の中で、本件従業員は、作業場所を確保するため、フォークリフトを前進ないし後退させる動作を繰り返したところ、段ボール等の可燃物がフォークリフトの車体の隙間に入り込み又はタイヤに巻き込まれてエンジンルームに混入し、高温になった排気管と接触して着火した、ということのようです。
3 主張の構造(不法行為構成と債務不履行構成)
⑴ 不法行為に基づく損害賠償請求(不法行為構成)
このような事案において、まず考えられるのは、当該作業を行っていた従業員に対する不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)と、その使用者である古紙回収業者に対する使用者責任に基づく損害賠償請求(民法715条第1項)かもしれません。
訴訟においては、不法行為の成立要件である行為者(本件では古紙回収業務を行っていた従業員)の故意または過失が存在したことの立証責任は、損害賠償を請求するアスクルにあるとされます。
⑵ 債務不履行に基づく損害賠償請求(債務不履行構成)
そのため、古紙回収業者自身の債務不履行、すなわち、古紙回収業務を継続的に行う契約において、古紙回収業務を適切に行い、債権者(アスクル)の財産権を侵害しない、という契約上の責任に違反した、とする債務不履行責任に基づく損害賠償請求(民法415条第1項)を行うのが一般的です。
債務不履行構成においては、適切な業務が遂行されなかった(債権者の財産を侵害した)ということは債務者に過失があったということが推定され、債務者に過失がなかったことの立証責任が転換されることになります。
5 裁判所の判断
⑴ 東京地裁
ア 本件従業員の過失
被告の従業員は、本件端材室に段ボールが集積されたままの状態で、フォークリフトを前後させる動作を繰り返せば、これによって、フォークリフトの周囲に集積された段ボール等の可燃物が車体の隙間に入り込み又はタイヤに巻き込まれてエンジンルームに混入し、高温になった排気管と接触して着火する可能性があることを予見し得たものというべきであるから、…被告の従業員には、本件火災の発生につき過失があったものと認めるのが相当である。
イ 損害額
(ア) 原告(アスクル側)の過失についての評価
・倉庫の火災報知設備が鳴ったにもかかわらず、誤作動によるものと誤解して2回にわたり同報知設備のスイッチを切ったこと
・原告の従業員が119番通報を行ったのはその約7分後であったこと
・原告の従業員は、最寄りの屋外消火栓からホースを延伸してバルブを開放したが、ポンプ起動ボタンを押さなかったためにポンプが起動せず、規定の水圧及び水量が得られなかったこと
このことに加え、同日午前9時頃の時点で本件端材室に集積されていた段ボールが高さ 1.5メートルないし3メートルに達していたことなど、本件火災による損害の拡大に寄与した原告側の事情を斟酌して、損害の公平な分担の見地から、…損害賠償責任を2割減じるのが相当である。
(イ)保険金の取扱い
原告は、本件火災による損害の填補として保険金49億7379万7258円を受領したことが認められるから、本件火災により原告が被った損害の額は、…(上記2割を減じたうえで)上記保険金の額を控除した残額50億9306万7388円となる。
⑵ 東京高裁
地裁の判決に対して、原告被告双方とも自身の敗訴部分について不服があるとして東京高裁に対して控訴しました。
ア 本件従業員の過失
「本件フォークリフトの取扱書には、取扱いの注意として、 「可燃物付近で車両を使用したり、止めたりしないでください。」、「車両後方や排気管付 近に燃えやすいものがあると、火災になるおそれがあります。」、「燃えやすいものの付近や上に車両を乗り入れたり、駐車したりしない。」」等の記載がされていた。
本件においては、本件従業員が「段ボールの散乱している本件端材室内において、 本件フォークリフトを運転し、その前進と後退を繰り返したことにより、エンジン始動後まもなくして高温となっていた同車両の排気管と段ボールが接触して発火し、これにより本件火災が発生したものと認められ…上記の発火について、 上記従業員には過失(予見可能性)があったと認められる。」。
ポイント
本件従業員の過失の認定の前提として、本件フォークリフトの取扱い説明書にエンジン分の付近に燃えやすいものがあれば発火の可能性があることが記載されており、本件フォークリフトを取り扱う者としては発火の予見可能性があったとされました。
イ 損害額
(ア) 原告(アスクル側)の過失についての評価
「本件フォークリフトを運転していた従業員の過失の程度が重くないことを考慮すると、損害の公平な分担の観点から、1審原告(アスクル)の過失割合を3割5分と認めた過失相殺を行うのが相当である。」。
(イ) 保険金の取扱い
「1審原告(アスクル)は同社が損害保険会社との間で締結していた保険に基づき当該損害保険会社から49億7379万7258円の本件火災による保険金を受領しているものの、これは 損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除すべき利益にはあたらない。」。
(ウ) 結論
「1審原告の請求は、94億2638万9260円及びこれに対する令和2年2月8日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で認容」する。
ポイント
高裁は、アスクルの従業員が火災報知機が鳴ったのを誤作動と考えて2回切ってしまったこと、定期的な火災訓練が行われておらず初期対応に遅れが見られたことに加え、段ボールの堆積状態及び本件倉庫の構造上そのような堆積状態ができるような構造となっていたこと等をも過失相殺の認定に加え、アスクルの過失認定割合を3割五分としました。地裁における過失認定割合が2割でしたのでアスクルの過失認定割合は増えたといえます。
しかしながら、高裁においては、保険金はアスクルが損害保険会社との契約に基づき保険料を支払っていた結果、アスクルに対して支払われたものであるので、損害額から減じられるべきではないとして、損害額から減じませんでした。
結果として、過失割合の認定では大きくなったものの、損害賠償賠償額は約94億円となりました。
6 教訓
⑴ 取扱説明書の遵守の重要性
高裁では、取扱説明書の記載を守っていなかったことが過失の原因のひとつとして認定されていました。自己防御のために取扱説明書にかかれていることは遵守しましょう。
⑵ 従業員教育
どのような状況によりどのような事故が発生してしまう可能性があるかを伝え、そのような事故の発生を防ぐために撮りうる手段を伝える必要があります。
⑶ 定期的な防災訓練
アスクル側の過失として、定期的な消防訓練が行われていなかったことも指摘されており、定期的な消防訓練も必要です。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
