INDUST2025年9月号に「令和7年6月24日『今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間とりまとめ』~その2~」が掲載されました
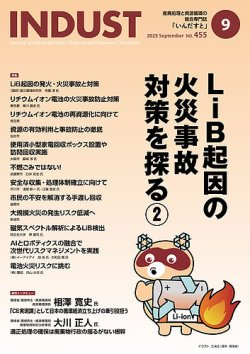
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2025年9月号に「令和7年6月24日『今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間とりまとめ』~その2~」が掲載されました。
今回は2017年の改正およびそれ以降に行われた制度的手当等を踏まえ、見直しが検討されている事項をご紹介したいと思います。
見直しが検討されている3点
・不適正ヤード問題への対応
・PCB廃棄物に係る対応
・災害廃棄物への対応
2.見直し検討事項
⑴不適正ヤードへの対応
ア 現行制度について
廃棄物に該当しない内部に有害物質が含まれる電気電子機器について、環境保全措置が十分に講じられないまま破砕や保管をされることにより、生活環境保全上の支障が発生していたことから、2017年の廃棄物処理法の改正により、有害使用済機器保管等届出制度が創設されました。
同制度においては、当該機器の保管または処分を業として行う場合に届出が義務付けられました。同制度の対象となる機器は、家電リサイクル法および小型家電リサイクル法の対象機器とされています。
イ 現行制度の問題点
もっとも、現行制度においては、有害使用済機器保管等届出制度の対象外である雑品スクラップ等について、保管場(ヤード)における不適正な処理に起因する騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災の発生等が報告されています。
また廃鉛蓄電池や廃リチウムイオン電池については、鉛の流出や火災等が多く報告されており、生活環境保全上の支障が生じているだけでなく、廃鉛蓄電池については、不適正に解体され、得られた鉛原料が不正に輸出される事例が報告されています。これによって国内における適正処理に支障をきたしているだけでなく、輸出先において環境上不適正に取り扱われるおそれが生じているとされています。
ウ 今後の検討における方向性
① 具体的な制度設計の方向性
② 許可制の導入の検討
③ 鉛蓄電池の取扱いについて
④ 国内資源循環と適正な事業者への配慮
エ 検討事項
① 制度の対象となる物品
・ 廃鉛蓄電池等
個々の物品に鉛等の有害物質が含まれ、その不適正な保管・処理により生活環境保全上の支障を生じるおそれのあるもの
・ 金属スクラップや雑品スクラップ等
一定程度集積して保管・処理されることにより生活環境保全上の支障を生じるおそれのあるもの
② 制度の内容
廃鉛蓄電池等であるか金属スクラップや雑品スクラップ等であるかによって、それぞれの性質に応じた規制を検討すべきであるとされています。
③ 適正処理の実効性を高めるための措置(トレーサビリティの構築)
制度の対象物品の受入れや処分に係る日付や数量等について、帳簿への記載を義務付けること等により、トレーサビリティの仕組みを構築すべきであるとされています。
④ 適正処理の確保により不適正輸出を防止するための仕組み
廃鉛蓄電池等については、廃棄物処理法上の廃棄物の取扱いに準じて、輸出に当たっては環境大臣の確認を受けなければならないことを検討すべきとされています。
⑤ 制度の実効性を高めるための措置(罰則等の強化)
オ 視点
従来、有害使用済機器の規制は、生活環境保全上の視点から行われていましたが、今回の見直しにあたっては、生活環境保全の視点とともに、循環経済の要請のもとで国内資源循環の確保、国内経済保障(国内で資源を確保することによって海外の諸事情から国内経済が維持されること)の視点が加えられたといえます。
⑵ PCB廃棄物に係る対応
ア PCBとは
① PCBの性質と法規制
PCBとは、昭和47年(1972年)に使用が禁止された人工の化学物質です。環境中で分解されにくく残留有機汚染物質(POPs)として長期間残存すること、生物への蓄積性があるという性質を有します。
② PCB廃棄物に関する廃棄物処理法とPCB特措法の関係
廃棄物処理法は、PCB使用廃棄物の適正処理を規制したものであり、PCB特措法は、PCBの期限内処理確保のための特別措置を定める特別法です。
PCB特措法において、PCB使用廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、高濃度PCB廃棄物はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)が処理することとなっています。
低濃度PCBに関しては、令和9年3月31日が処理期限とされています。
⑶ 現行制度の問題点(制度的手当ての必要性)
今後、廃屋の解体工事等により予期せず高濃度PCB廃棄物が発見される等、少量ずつ散発的に高濃度PCB廃棄物が発生する可能性があります。
また、低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月の処理期限後に、製品寿命等により新たに低濃度PCB廃棄物が発生すること等が見込まれるため、低濃度PCBの適正な管理及び処理が実施されるよう制度的手当てが必要となります。
⑷ 今後の検討における方向性
PCB特措法等において、高濃度PCB廃棄物の継続的な処理体制の確保、低濃度PCB含有製品等に係る管理を強化する措置、自治体等による低濃度PCB含有廃棄物等の管理に係る措置を講ずることにより、POPs 条約で求められている令和10年までのPCBの適正な管理を実現することが求められます。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
