INDUST2022年12月号に「プラ新法と廃棄物処理業界のチャレンジ」が掲載されました
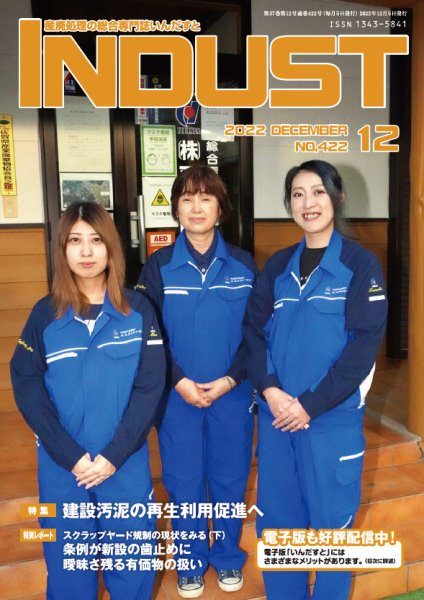
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2022年12月号に「プラ新法と廃棄物処理業界のチャレンジ」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2332197/
本年4月にプラスチック資源循環促進法は、社会に大きなインパクトを与えました。今回は、プラ新法が現在、どのように具体化されているか、企業のプラ新法に対する取組み方などを概観してみたいと思います。
プラ新法は、プラスチック資源循環に取り組むための事業計画を立て、環境省から認定を得ると、その資源循環を実行するための行為については、廃棄物処理法上の許可を要しないとする法律です。すなわち、許可業者からみれば、許可で守られていた職域に他業種が許可なく参入が認められることとなり、一見すると、メリットがないように思われるかもしれません。しかしながら、本法は、製造業者等に対してだけではなく、廃棄物処理業界にとっても大きなビジネスチャンスを生む法律であるとともに、ビジネスの転換点となり得る法律だと思います。
例えばプラスチックの製造事業者等は、自主回収・再資源化事業計画について自らが認定を受けることができれば、廃棄物処理法上の許可を受けることなく、プラスチック廃棄物の収集運搬及び中間処理を行うことができます。
東京都の公募により採用された花王株式会社による例をご紹介したいと思います。花王は、2020年9月から2021年2月の期間において、トイレタリー商品の包装容器の製造にあたって、環境に配慮した「単一素材」(モノマテリアル)の詰め替え用フィルム容器、再生プラスチックを製造し、これを公共施設に直接配送し、公共施設で使用した後、回収し、同一素材を使って高品質な再生プラスチック製品(「水平リサイクル」)を製造するという実証実験を行いました。
この実証実験は、花王が資源循環型製品および資源循環型システムの全体設計を実施し、凸版印刷が、資源循環型の単一素材(モノマテリアル)のつめかえ用フィルム容器を製造し、市川環境エンジニアリング(および同社協力法人)において、加工しやすい再生ペレットの開発ならびに、ペレットを使用した資源循環型ボトル容器の開発を担当するなど、複数の企業の協力関係において成立しています。
とくに着目していただきたいのは、再生ペレットの開発ならびに資源循環型ボトル容器の開発を廃棄物処理業者(市川環境エンジニアリング)が担っている点です。再生ペレットの開発ならびに資源循環型ボトル容器の開発は、本実証実験の核となる部分といえますが、まさに廃プラスチックの中間処理を業務として行ってきた廃棄物処理業者のノウハウが活かされるところです。
このように、製造事業者等による再資源化事業は、多くの場合、企業単独で行われるものではなく、他の業者、とくに廃棄物処理の技術とノウハウを持つ廃棄物処理業界との協力が大きく期待されるところです。プラ新法の施行だけでなく、SDGsやESG投資の視点から企業は自社の商品の再資源化に意欲的です。廃棄物処理企業としては、受託型ではなく、積極的に再資源化事業を提案し、企業との再資源化事業のコラボレーションにチャレンジしていただきたいです。
また市町村が分別収集したプラスチック容器廃棄物は、容リ法の指定法人に引き渡して再商品化されていましたが、プラ新法の下では、市町村が再商品化計画を立案し、独自でリサイクルを行うことができます。今回は仙台市による例をご紹介します。従来は、プラスチック製包装容器のみ指定法人に引き渡され、リサイクルされる一方で、それ以外のプラ製品廃棄物については家庭ごみとして焼却処理されていたところ、プラ容器とプラ製品廃棄物を一括して回収し、協力処理業者(J&T株式会社)の市内施設において、選別からリサイクルまでの工程を一体的に行い、プラスチック製品の原料となるペレットやフラフ等にリサイクルし、同施設においてこれらの原料を利用して、物流パレットを製造します。
本稿ではより詳しく解説していきます。
是非ご覧ください。
